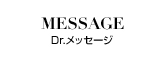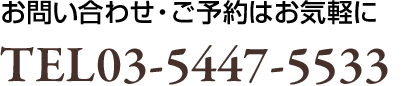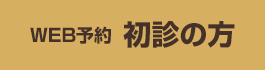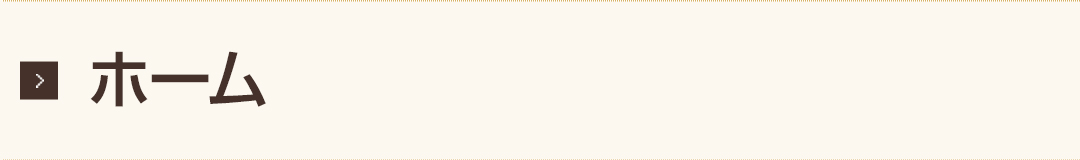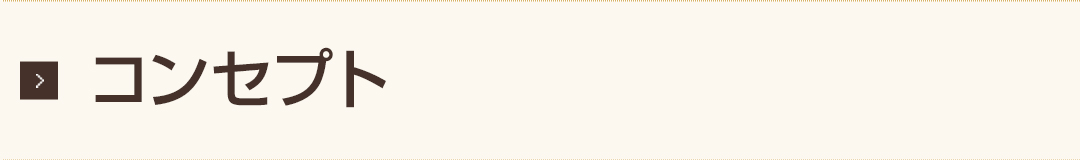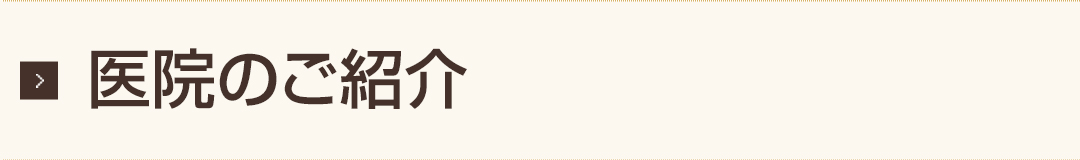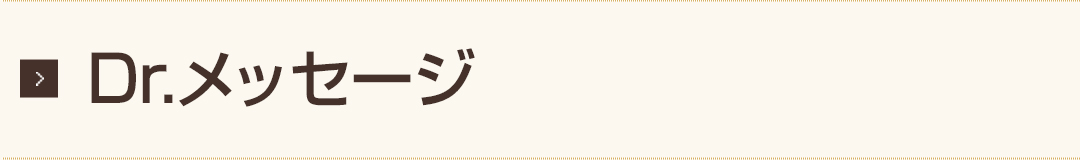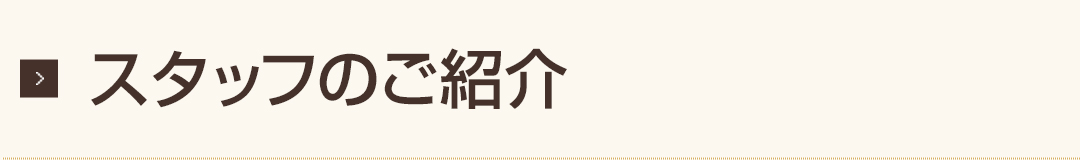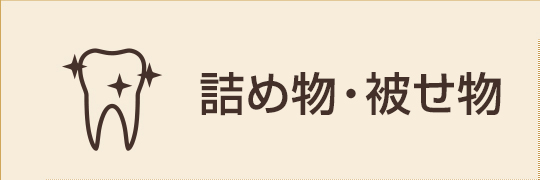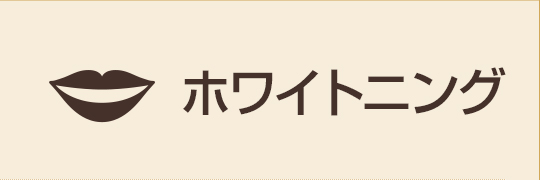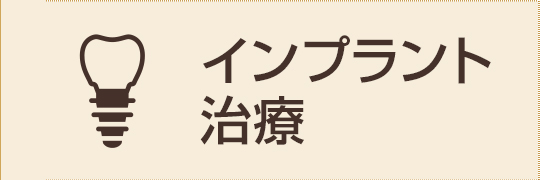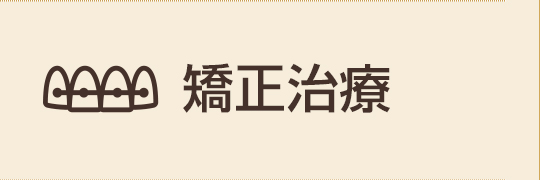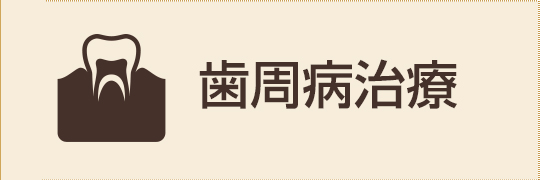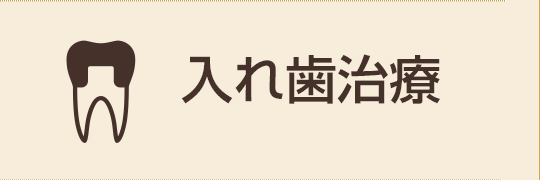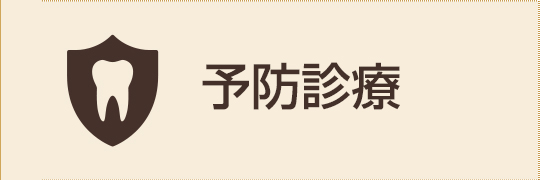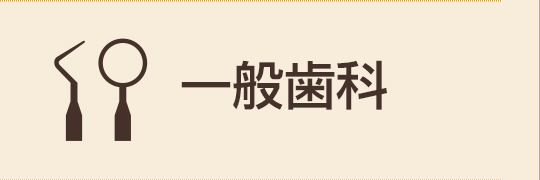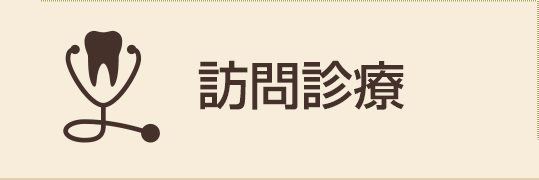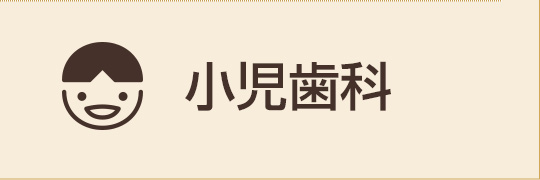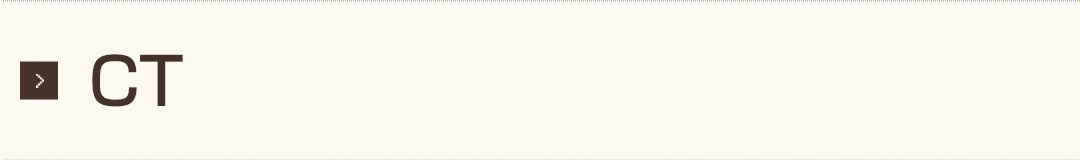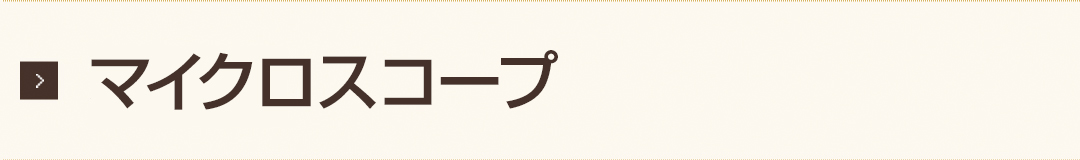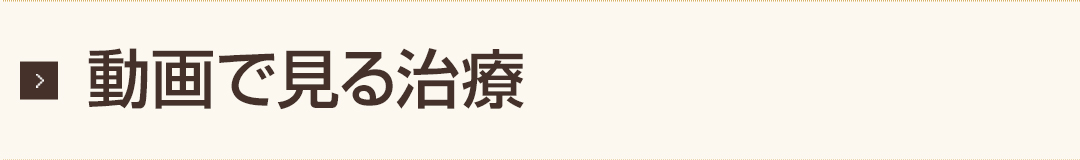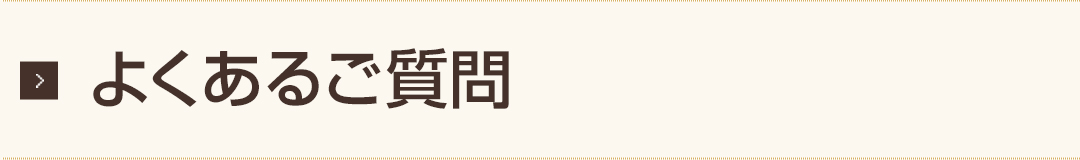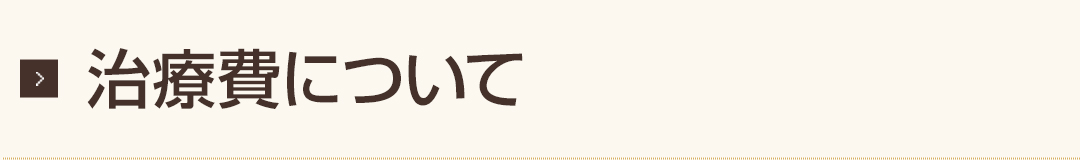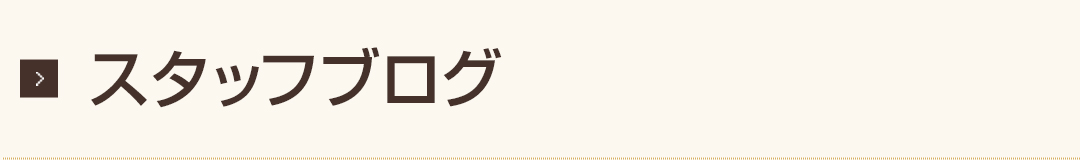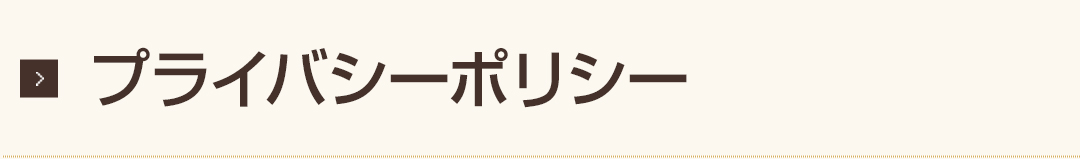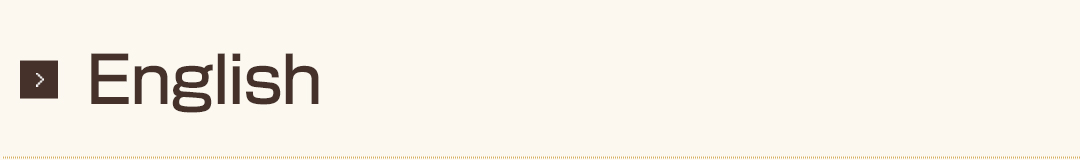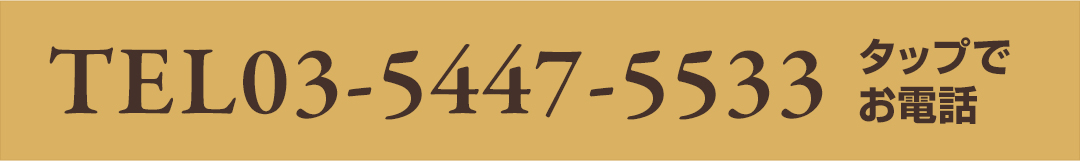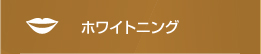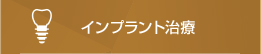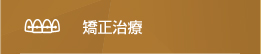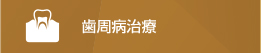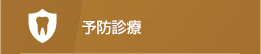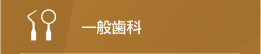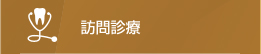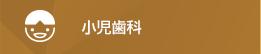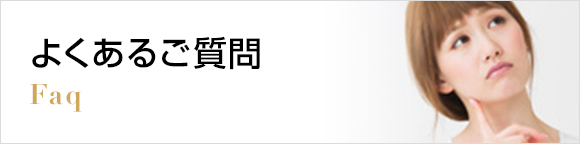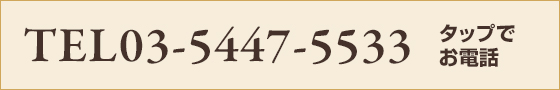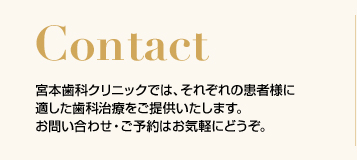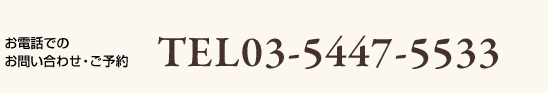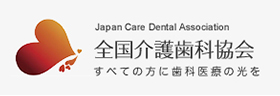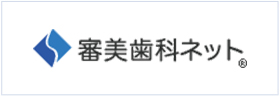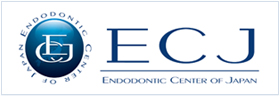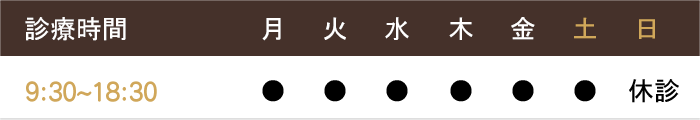プラークコントロールを評価する「PCR値」とは
2024/08/13
今回は、プラークコントロールを評価する「PCR値」についてご紹介します。「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「口腔内の細菌叢の改善」があります。細菌叢のバランスを保つために必要となるのが「プラークコントロール」です。プラークコントロールの評価方法として知られている「PCR値」は、歯の健康を維持するための重要な指標であるのをご存じですか?
PCR値とは?
PCR値(Plaque Control Record)は、口腔内のプラーク(歯垢)の付着状態を評価するための指標です。歯科医師や歯科衛生士が、患者様の歯の表面にどれだけプラークが付着しているかを調べ、その結果を数値化します。PCR値は、プラークが付着している歯の表面の割合を示し、パーセンテージで表されます。この数値が低いほど、プラークコントロールが良好であることを示しています。
PCR値の測定方法
PCR値の測定は、次のような手順で行われます。
- 染色液の塗布
プラークを染め出すために、専用の染色液を歯に塗布します。染色剤はプラークに反応し、目に見えるように色が付きます。
- 観察と記録
染色されたプラークを歯科医師もしくは歯科衛生士が観察し、それぞれの歯の表面(頬側、舌側、歯間など)に付着しているプラークの有無を専用の用紙に記録します。
- 評価
記録されたプラークの付着部位数を、全体の歯面数で割り、パーセンテージを計算します。これがPCR値となります。
PCR値の目安
プラークコントロールが良好に行われていると判断されるPCR値は、20%以下です。プラークはむし歯や歯周病の主な原因となる細菌の集まりであるため、この数値が低ければ低いほど、むし歯や歯周病のリスクは低いといえます。一見この数字だけを見るとすぐに達成できそうだと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、しっかり磨いているつもりの方でもPCR値の検査をしてみたら50%を超えていた、ということも実は珍しくありません。したがって、歯と歯の間など隅々まで歯を磨くということが、プラークコントロールにおいて非常に重要であるということです。
まとめ
PCR値は、プラークコントロールの状態を数値で把握するための重要な指標です。毎日のセルフケアと定期的な歯科検診を通じて低いPCR値を維持することが、むし歯や歯周病を予防し、歯とお口の健康をを守るために大切です。
当院ではミニマルインターベンション(MI)の考え方に基づき、患者さまお一人おひとりにとって最善の治療方法をご提案しております。ご予約、お問合せはお電話で承っております。
ダイレクトボンディング後の食事で気をつけたいこと
2024/08/09
今回は、ダイレクトボンディング後の食事で気をつけたいことについてご紹介します。ダイレクトボンディングは歯の修復や審美面の改善に広く用いられている治療方法ですが、治療後の着色には注意が必要です。特に食事については、着色や変色を防ぐために気をつけるべきポイントがあります。
着色には要注意
当院のダイレクトボンディングに使用しているハイブリッドレジンは比較的着色しにくい素材として知られていますが、絶対に変色しないわけではありません。レジンには吸水性があるため長期間にわたって飲食物の色素を吸収し、変色する可能性があります。ダイレクトボンディングの美しい仕上がりを長持ちさせるためには、日常の食事で着色しないように注意が必要です。
気をつけたい食べ物、飲み物
以下のような飲食物を長期間にわたって摂取すると、レジンの色に影響を与える可能性があります。
・色の濃い飲食物
コーヒー、赤ワイン、ソース類(醤油、カレー)、ベリー類(ブルーベリー、ラズベリー)など
・着色しやすい成分を含む飲食物
ポリフェノールを含む食品(お茶、チョコレート)、イソフラボンを含む食品(豆乳、納豆)など
着色しやすいものを飲食したあとに気をつけたいこと
着色しやすいものを摂取した後には、以下のような対策を取りましょう。
・水で口をゆすぐ
飲食後にすぐに水で口をゆすぐことで、色素が歯に付着するのを防ぐことができます。特に色の濃い飲み物を摂取した後は、早めに口をゆすぐように心がけましょう。
・就寝前には着色しやすいものを飲まない
就寝中は唾液の分泌量が減少して口腔内が乾燥する傾向にあるため、色素が歯に付着しやすくなります。寝る前に着色しやすい飲み物を飲むのは避け、就寝前には水や無色透明の飲み物を選ぶと良いでしょう。
・歯磨きはゴシゴシ磨かず優しく
歯磨きをするときはゴシゴシと強く磨かず、優しく磨くことが大切です。強く磨くとレジン表面が傷つき、逆に着色しやすくなることがあります。
まとめ
このように、ダイレクトボンディング後の美しい仕上がりを長持ちさせるためには、日頃の食事にも注意が必要です。食後は適切なケアを行うことで、健康で美しい歯を維持することができます。当院では患者様のお口の中の状況に合わせた治療方法をご提案いたしますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
歯科医院でクリーニングを受ける頻度
2024/08/07
今回は、歯科医院でクリーニングを受ける頻度についてご紹介します。歯をなるべく削らない治療「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「口腔内の細菌叢の改善」があります。プラークや歯石を確実に除去するために歯科医院で定期的にクリーニングを受けることは大切ですが、どのくらいの頻度でクリーニングを受けるべきなのでしょうか。
クリーニングを受ける頻度は人によって異なる
歯石のつきやすさやむし歯、歯周病のリスクには個人差があります。例えば、唾液の質や量、食生活、日常のセルフケアの習慣などが影響します。これにより、クリーニングの頻度も異なります。一般的には、むし歯になりやすい人や歯周病にかかっている人は、あまり間隔をあけずに定期的にクリーニングを受けることが推奨されます。
3~6ヶ月に一度のクリーニングが適している人
歯石がつきにくくセルフケアがしっかりできている人は、3~6ヶ月に一度のクリーニングが適しています。歯科医院での定期的なチェックとクリーニングを行うことで、むし歯や歯周病のリスクを低く保てるでしょう。セルフケアに自身があってもプロフェッショナルによるクリーニングを受け、見逃しがちな初期のトラブルを早期発見できる可能性があります。
2~3ヶ月に一度のクリーニングが適している人
歯石がつきやすい人、着色がつきやすい人、歯並びがよくない人、そして歯磨きが苦手な人は、2~3ヶ月に一度のクリーニングが推奨されます。歯石や着色は見た目だけでなくお口の中の健康にも影響を及ぼすため、定期的に除去することが重要です。また、歯並びが悪いと磨き残しが発生しやすく、歯磨きが苦手な人も同様にリスクが高いため、こまめなプロフェッショナルケアが必要です。
1~2ヶ月に一度のクリーニングが適している人
むし歯になりやすい人や、すでに歯周病にかかっている人は、1~2ヶ月に一度のクリーニングが必要です。頻繁にクリーニングを行うことで症状の進行を抑え、症状の改善を図ります。特に歯周病は進行すると治療が難しくなるため、早期の段階での管理が非常に重要です。
まとめ
今回は、歯科医院でクリーニングを受ける頻度についてご紹介しました。クリーニングを受ける頻度は個人のお口の中の状態やリスクに応じて異なります。それぞれの状態に合わせて適切な頻度でクリーニングを受け、より健康な歯と歯ぐきを保ちましょう。
当院ではミニマルインターベンション(MI)の考え方に基づき、患者さまお一人おひとりにとって最善の治療方法をご提案しております。ご予約、お問合せはお電話で承っております。
エナメル質形成不全にダイレクトボンディングは有効?
2024/08/05
今回は、エナメル質形成不全にダイレクトボンディングは有効なのかについてご紹介します。ダイレクトボンディングは歯の修復や審美面の改善に広く用いられている治療方法ですが、エナメル質形成不全によって生じている形態や色味の異常にも適応できるのでしょうか。
エナメル質形成不全とは
エナメル質形成不全とは、歯のエナメル質が正常に形成されない状態を指します。遺伝的要因もしくは後天的な環境要因によって引き起こされるもので、後者の場合は幼少期の栄養不良、発熱性疾患、薬物の副作用などが原因として挙げられます。この状態により、歯の表面に白色の斑点模様ができたり、変色したりすることがあります。
エナメル質形成不全によって起こり得ること
まず、歯の形や見た目に影響が出ることがあります。エナメル質が正常に形成されないため、歯が凹凸になったり、白斑や茶色の斑点が現れることがあります。また、エナメル質が薄く弱いため、むし歯になりやすいというリスクも高まります。むし歯が進行すると、歯の痛みやさらなる治療が必要になることがあります。
エナメル質形成不全にダイレクトボンディングは有効?
ダイレクトボンディングは、歯科用の樹脂を用いて歯の表面を修復する治療法です。エナメル質形成不全の範囲が比較的狭い場合、この方法は非常に有効です。
ただし、エナメル質形成不全の範囲が広い場合には、ダイレクトボンディングだけでは十分な修復が難しいこともあります。そのような場合には、クラウン(被せ物)での治療が適しています。この方法であればエナメル質が広範囲にわたって欠損している場合でも、歯の機能と見た目を回復させることができます。
まとめ
このように、エナメル質形成不全に対する治療方法の選択は、その範囲や程度によって異なります。軽度の形成不全であれば、ダイレクトボンディングも効果的な手段の一つであり、自然な見た目と機能を回復することができます。どの治療法が適しているかは、歯科医師との相談の上で決定するようにしましょう。当院では患者様のお口の中の状況に合わせた治療方法をご提案いたしますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
歯石がつきやすい場所
2024/08/02
今回は、歯石がつきやすい場所についてご紹介します。歯をなるべく削らない治療「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「口腔内の細菌叢の改善」があります。歯石は、口腔内の健康を維持する上で注意すべき重要な問題です。歯石はプラーク(歯垢)が硬化してできるもので、時間が経つと石灰化して硬くなるため歯ブラシで取り除くことが難しくなります。歯石がつきやすい場所を知り、日常のケアに役立てましょう。
唾液腺の開口部と歯石の関係
歯石がつきやすい場所は、主に唾液腺の開口部に近い部分です。唾液には、歯垢を中和する働きがある一方で、カルシウムやリン酸塩といったミネラルが含まれており、これらが歯垢と結びつくことで歯石が形成されやすくなります。そのため、唾液が多く分泌される場所、すなわち唾液腺の開口部付近は、特に歯石がつきやすいのです。唾液腺は唾液を分泌する腺で、主に3つの主要な唾液腺があります。それぞれの唾液腺は異なる場所に位置し、唾液の分泌量や性質が異なります。
・耳下腺
耳の前下方、顎の付け根あたりに位置しており、開口部は上顎の第一大臼歯の近くにあります。
・顎下腺
下顎の下側、顎の内側に位置しており、開口部は下顎の前歯の裏側、舌の付け根にあります。
・舌下腺
舌の下、下顎の前歯の裏側に位置しています。開口部は舌の下面にあります。
歯石がつきやすい場所
・下顎の前歯の裏側
下顎の前歯の裏側は、特に歯石がつきやすい場所の一つです。この部分は、舌下腺と顎下腺という二つの大きな唾液腺の開口部があり、唾液の分泌が盛んです。唾液が多く流れることで、ミネラルが歯垢と結びつき、歯石が形成されやすくなります。また、舌があるために歯ブラシが届きにくく、プラークが溜まりやすいことも原因の一つです。
・上の奥歯の頬側
上顎の奥歯の頬側も、歯石がつきやすい場所です。この部分には耳下腺の開口部があり、唾液の分泌が豊富です。特に奥歯はプラークが溜まりがちで、歯石が形成されやすくなります。奥歯の磨き残しを防ぐために、デンタルフロスや歯間ブラシを使うことが大切です。
まとめ
今回は、歯石がつきやすい場所についてご紹介しました。歯石がつきやすい場所は特に日々のケアを徹底し、歯石の予防に努めましょう。当院ではミニマルインターベンション(MI)の考え方に基づき、患者さまお一人おひとりにとって最善の治療方法をご提案しております。ご予約、お問合せはお電話で承っております。