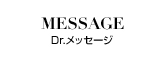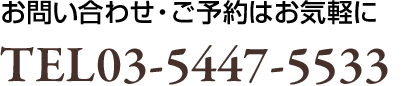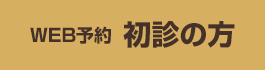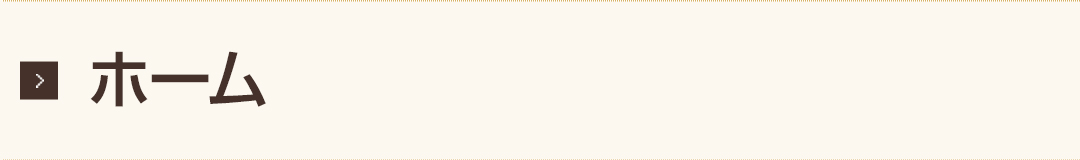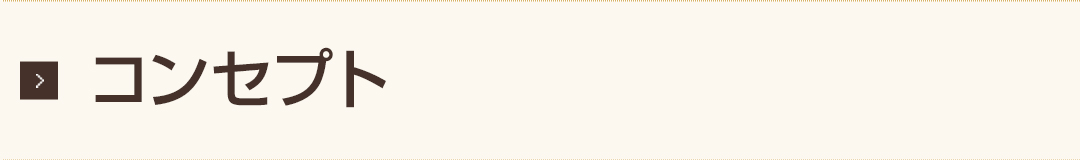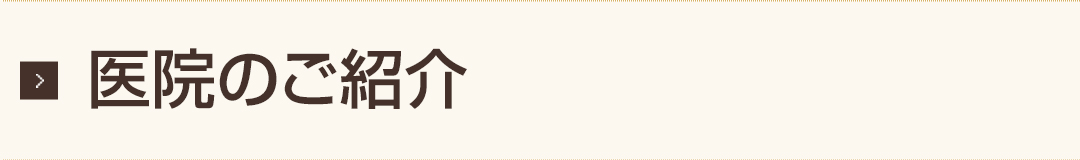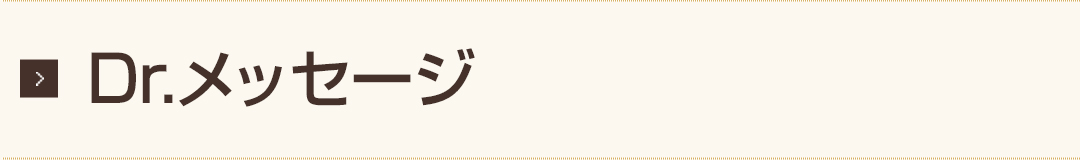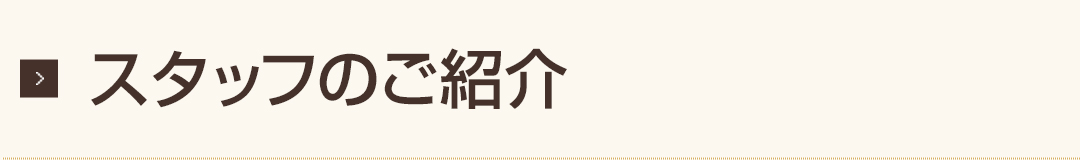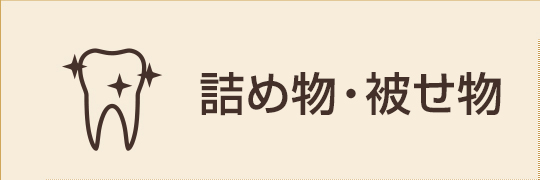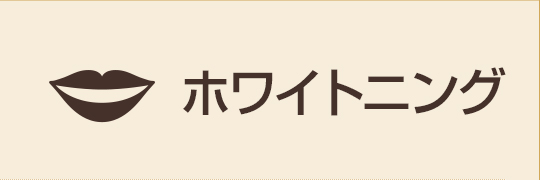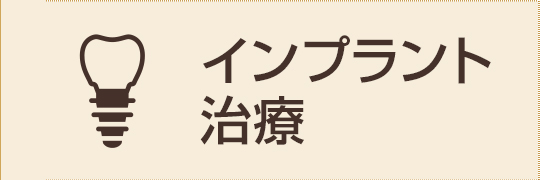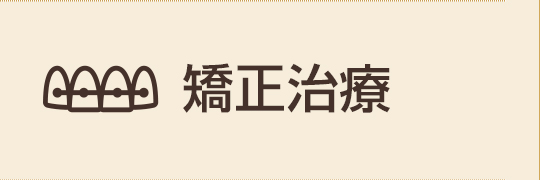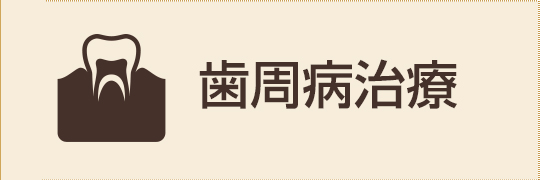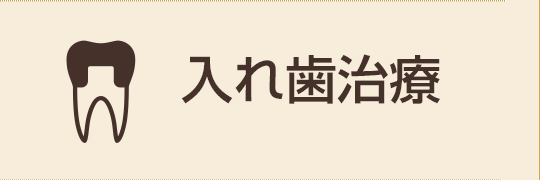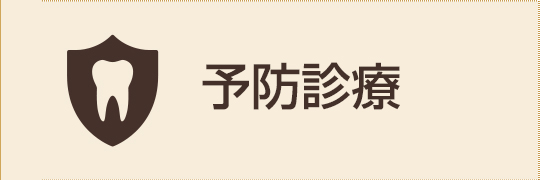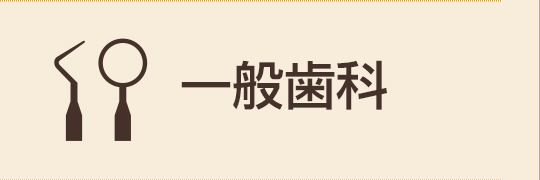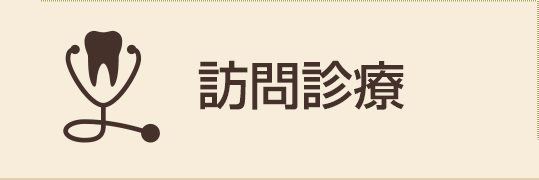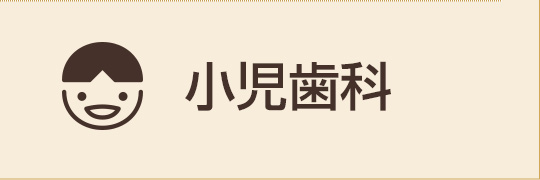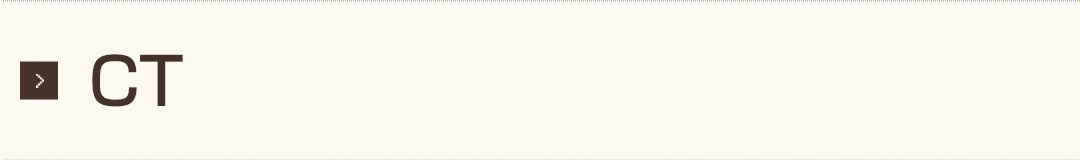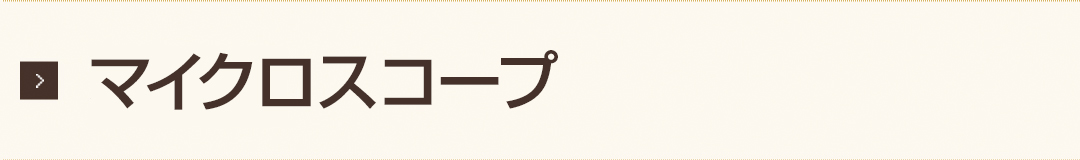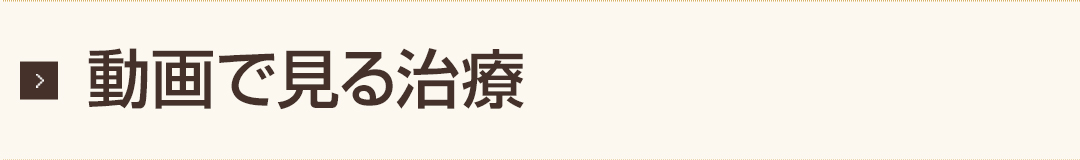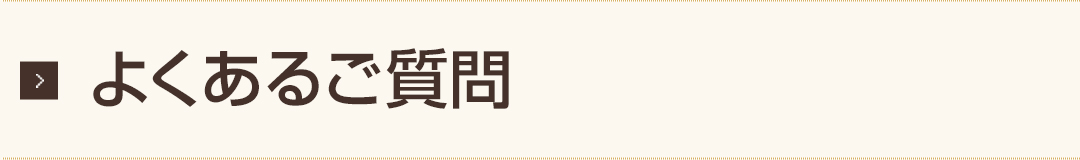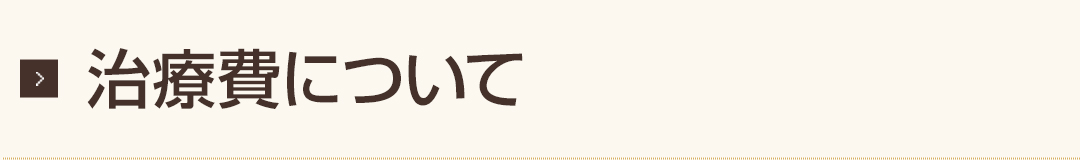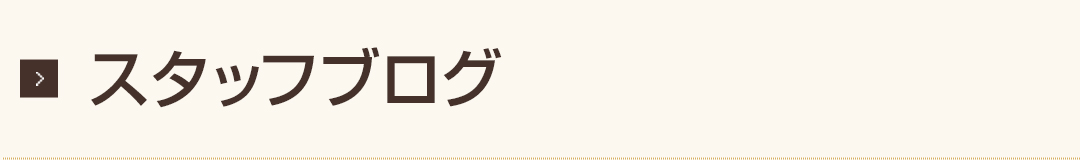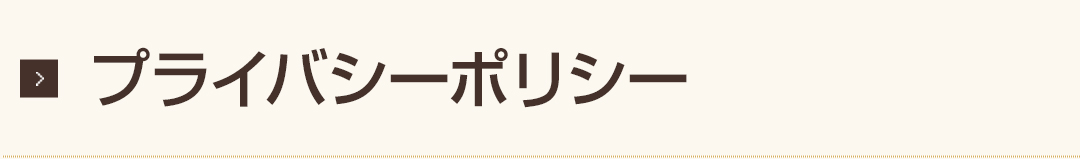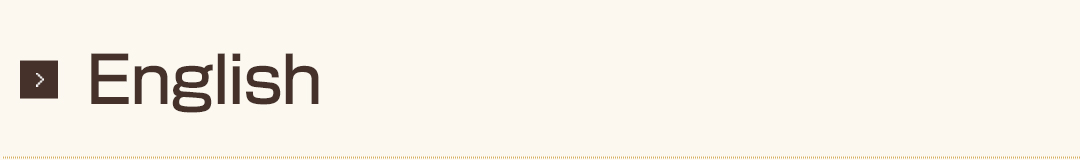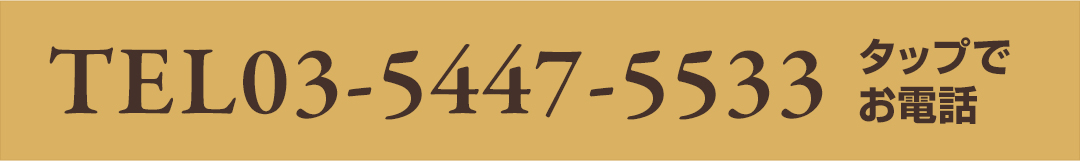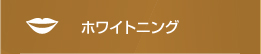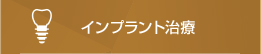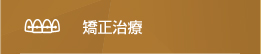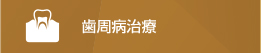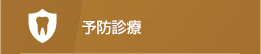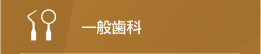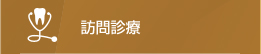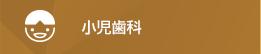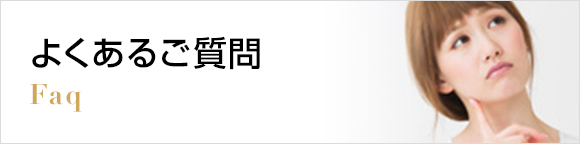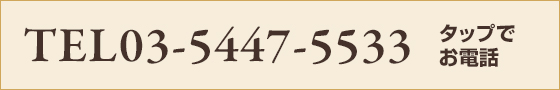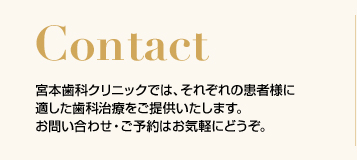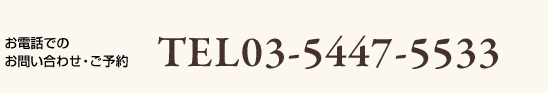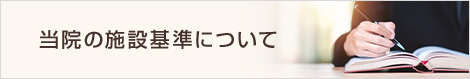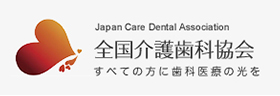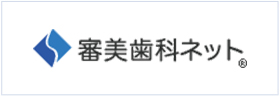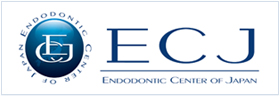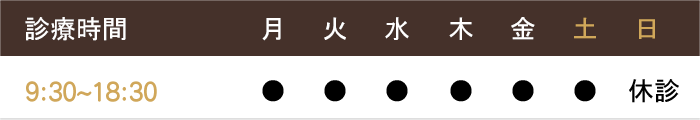むし歯治療に使われる「レジン」と「銀歯」の違い
2026/02/06
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、むし歯治療に使われる「レジン」と「銀歯」の違いについてご紹介します。
歯を最小限しか削らないレジン治療の特徴
むし歯治療でよく使われる材料のひとつが「レジン」です。レジンは歯科用プラスチックの一種で、歯の色に近いため、治療後も自然な見た目を保ちやすいのが特徴です。むし歯の部分だけをピンポイントで削り、その場で詰めて固めることができるため、健康な歯を削る量を最小限に抑えやすい治療法といえます。これは、歯をできるだけ残すことを大切にするミニマルインターベンションの考え方と非常に相性が良い材料です。また、治療回数が少なく済む点もメリットのひとつです。
強度に優れる一方、削る量が増えやすい銀歯
一方、「銀歯」は金銀パラジウム合金などの金属を使った詰め物・被せ物で、長年にわたり保険診療の中心として使われてきました。強度が高く、噛む力が強くかかる奥歯でも耐久性が期待できるというメリットがあります。ただし、銀歯を装着するためには、レジン治療に比べて歯を大きく削る必要がある場合が多く、健康な歯質まで削らなければならないこともあります。この点は、歯の保存を重視するミニマルインターベンションの視点では注意が必要なポイントです。
ミニマルインターベンションの視点で考える材料選択
ミニマルインターベンションでは、むし歯になった部分だけを取り除き、歯の再石灰化や修復力を最大限に活かすことが基本となります。そのため、初期〜中等度のむし歯であれば、歯を大きく削らずに済むレジン治療が第一選択となることが増えています。ただし、むし歯が深く進行している場合や、噛み合わせの力が強くかかる部位では、銀歯の方が適しているケースもあり、材料の選択は一概には言えません。
大切なのは「材料」よりも「歯を守る視点」
大切なのは、「どの材料が良い・悪い」ではなく、「その歯の状態にとって何が最も歯を守れるか」という視点です。むし歯の大きさ、部位、噛み合わせ、生活習慣などを総合的に考えたうえで治療法を選択することが、歯を長持ちさせることにつながります。
まとめ
当院では、ミニマルインターベンションの考え方を大切にし、できる限り歯を削らず、残せる治療をご提案しています。レジン治療と銀歯、それぞれの特徴を丁寧にご説明したうえで、お一人おひとりに合った治療法を一緒に考えていきますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。
むし歯は全部削らなくてもいい?ミニマルインターベンションの考え方
2026/01/09
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、ミニマルインターベンションにおけるむし歯治療の考え方についてご紹介します。
ミニマルインターベンションとは
ミニマルインターベンション(MI)の考え方では、むし歯になった部分を無条件に大きく削るのではなく、「削るべき部分だけを、最小限に取り除く」ことを重視します。むし歯の進行具合によっては、薬剤でむし歯菌の活動を抑えたり、歯の再石灰化を促したりすることで、削らずに様子を見るという選択肢もあります。特に初期むし歯は、フッ素の活用や正しいブラッシングにより、削らずに改善できることが多いのです。
すべてのむし歯を削る必要がない理由
むし歯治療で最も大切なのは「歯を長持ちさせること」です。削る量が増えると、詰め物は大きくなり、歯はもろくなりやすくなります。その結果、詰め物の下にむし歯が再発(2次むし歯)しやすくなり、再治療を繰り返していくうちに歯の寿命が縮んでしまうのです。MI治療では、この悪循環を避けるためにも、必要最小限の削除と予防管理を組み合わせ、歯を守ることを優先します。
MIに基づく具体的な治療方法
MI治療では、むし歯の進行度に応じた方法を選択します。軽度の場合は、経過観察やフッ素塗布で再石灰化を促すことがあります。進行している場合でも、むし歯菌が侵食した「軟らかく汚染された部分」だけをピンポイントで取り除き、健康な歯質はできるだけ残すよう努めます。また、近年では高性能な接着材が発達しており、大きく削らなくても強度を保てる治療が可能になりました。
むし歯を作らない生活習慣もMIの一つ
ミニマルインターベンションは、削らない治療だけを指しているわけではありません。そもそも“むし歯を作らないようにすること”も非常に重要な要素です。正しいブラッシング、フッ素入り歯磨き粉の使用、間食のコントロール、そして定期的な歯科検診は、歯を削らずに済む最も効果的な方法といえます。
まとめ
むし歯は必ずしも「すぐに削らなければいけない」ものではありません。ミニマルインターベンションの考え方に基づく治療では、歯をできるだけ残し、将来にわたって健康な歯を維持することを目指しています。歯を残す治療に興味のある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
マスク生活でむし歯が増える?これからの時期に気をつけたい口呼吸との関係
2025/12/05
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、マスク生活とむし歯リスクの関係についてご紹介します。
口呼吸とお口の健康は関係がある?
季節が冬へと近づく11月〜2月は、風邪やインフルエンザの流行が増え、マスクを着ける時間が長くなる方が多い時期です。感染予防として大切なマスクですが、実は知らないうちにお口の健康へ影響を与えてしまうことがあります。その要因のひとつが、マスクによって起きやすくなる「口呼吸」です。
マスクで口呼吸が増える理由
普段の呼吸は鼻が基本ですが、マスクを長時間つけていると、息苦しさから無意識に口で呼吸する習慣がつきやすくなります。特に運動中や会話が続くと、口が自然と開いた状態になり、気付かぬうちに口呼吸がクセになってしまうこともあります。
口呼吸はなぜむし歯のリスクになる?
口呼吸になると、お口の中が乾燥しやすくなります。鼻呼吸は空気を加湿・加温してから肺に送るため、口腔内は乾燥しにくい状態に保たれます。しかし口呼吸の場合、乾いた空気が直接お口の中に流れ込み、唾液が蒸発しやすくなります。
唾液には、むし歯菌が作り出す酸を中和する働きや、洗い流す自浄作用があります。ところが乾燥によって唾液量が減ると、歯に歯垢(プラーク)がたまりやすくなり、むし歯菌が活発になるため、むし歯のリスクが高まってしまうのです。さらに乾燥は、歯ぐきの炎症や口臭にもつながることがあります。
口呼吸のサイン、気づいていますか?
「朝起きると口がネバネバする」「喉が乾きやすい」「気づくと口が開いている」といった気付きは、口呼吸の可能性があるサインです。マスクをしていると周囲から見えにくいこともあり、自分では気付きにくいケースもあります。
むし歯を防ぐためにできる対策
口呼吸を予防するうえで大切なのは、「意識すること」です。パソコン作業やスマートフォンを見るとき、口が半開きになっていないかチェックしてみましょう。また、舌先を上あごに軽く当てる姿勢を意識すると、鼻呼吸がしやすくなります。乾燥が気になる場合は水分補給をこまめに行うことも効果的です。唾液を増やすために、無糖のガムを噛む・キシリトール製品を利用するといった方法もあります。ただし砂糖入りのお菓子や飴は逆にむし歯リスクを高めてしまうため注意しましょう。
まとめ
冬はマスクだけでなく、暖房による空気の乾燥でお口の水分が失われやすい季節です。風邪対策と同じように、お口の健康も意識して過ごすことで、むし歯や歯周病のリスクを減らすことができます。
早めのチェックで、トラブルを未然に防ぎましょう。
むし歯とストレスの意外な関係
2025/11/21
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、むし歯とストレスの意外な関係についてご紹介します。
ストレスが唾液の量を減らす
強いストレスを感じると、自律神経のバランスが崩れ、交感神経が優位になります。その結果、唾液の分泌が減少し、口の中が乾燥しやすくなります。唾液には、むし歯菌の働きを抑えたり、酸を中和したりする重要な役割があります。唾液が少なくなると口内が酸性に傾き、むし歯菌が増えやすい状態になってしまうのです。
生活習慣の乱れもむし歯の原因に
ストレスが続くと、生活リズムが乱れがちになります。食事の時間が不規則になったり、間食が増えたり、歯みがきを忘れてしまったり、といった小さな乱れが積み重なることで、むし歯リスクは高まります。特に夜遅くの飲食後にそのまま寝てしまうと、唾液の分泌が少なくなる就寝中に細菌が活発に働き、むし歯が進行しやすくなります。
歯ぎしり・食いしばりにも注意
ストレスは「歯ぎしり」や「食いしばり」といった無意識のクセを引き起こすこともあります。これらの習慣によって強い力が歯にかかると、歯の表面に細かいヒビが入り、そこから細菌が侵入してむし歯になる場合があります。歯や顎の痛み、知覚過敏などを感じたら、早めに歯科を受診しましょう。
ストレス対策でお口の健康を守る
ストレスによるむし歯を防ぐには、まず心身のバランスを整えることが大切です。睡眠をしっかり取り、趣味や運動などでリフレッシュする時間を設けましょう。また、口の中の乾燥を防ぐために、水分補給をこまめに行う・ガムを噛む・口呼吸を控えるなどの工夫も効果的です。
まとめ
むし歯は食生活だけでなく、ストレスとも深い関係があります。むし歯や歯ぎしりの初期サインは、自分では気づきにくいものです。定期的に歯科医院でチェックを受けることで、ストレスによるお口のトラブルを早期に発見・予防しましょう。
スポーツドリンクとむし歯 運動習慣のある人が気をつけたいこと
2025/10/24
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、運動習慣のある方に知っていただきたいスポーツドリンクとむし歯の関係についてご紹介します。
スポーツドリンクでむし歯リスクが高くなる?
運動をするとき、のどの渇きを癒やすために「スポーツドリンク」を飲む方は多いのではないでしょうか。発汗で失われた水分やミネラルを補給できるため、運動時のパフォーマンス維持や熱中症予防に役立ちます。しかし一方で、スポーツドリンクの飲み方次第では「むし歯のリスク」を高めてしまうことがあります。
スポーツドリンクがむし歯を招きやすい理由
スポーツドリンクには糖分が多く含まれているのをご存知でしょうか。一般的な500mlペットボトル1本には、角砂糖10個分以上の糖分が入っているものもあります。運動中に少しずつ飲むことで、口の中は長時間「砂糖水でうがいしている状態」になり、むし歯菌が活発に働きやすくなるのです。
さらに、スポーツドリンクは酸性度が高い飲み物でもあります。酸性の飲料は歯の表面(エナメル質)をやわらかくし、酸に弱くなった歯に糖分が加わることでむし歯が進行しやすい環境が整ってしまいます。これを酸しょく症と呼び、むし歯だけでなく歯の摩耗や知覚過敏の原因にもつながります。
運動習慣がある人が注意したい飲み方
「それならスポーツドリンクは飲まない方がいいの?」と思うかもしれません。もちろん、強度の高い運動や炎天下での活動ではスポーツドリンクが有効な場面もあります。ただし、次の点に気をつけることで、むし歯リスクを抑えることができます。
・だらだら飲まない:長時間少しずつ飲むのではなく、休憩のタイミングで必要量をまとめて飲むようにしましょう。
・飲んだ後は水でうがい:スポーツドリンクを口にした後に水でうがいをすることで、酸や糖を洗い流せます。
・就寝前は避ける:寝る直前にスポーツドリンクを飲むと、唾液分泌が減る睡眠中にむし歯リスクが高まります。
・普段の水分補給は水やお茶で:日常的なトレーニングや軽い運動では、水や麦茶で十分に対応可能です。
まとめ
スポーツドリンクは、適切に活用すれば運動時の強い味方になりますが、飲み方を誤るとむし歯や酸蝕症のリスクを高めてしまいます。大切なのは、必要な場面で正しく使うことと、飲んだ後のケアを忘れないことです。運動習慣のある方こそ、健康な歯を守りながら長くスポーツを楽しめるように意識していきましょう。