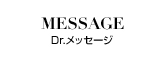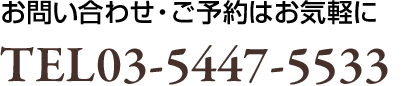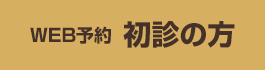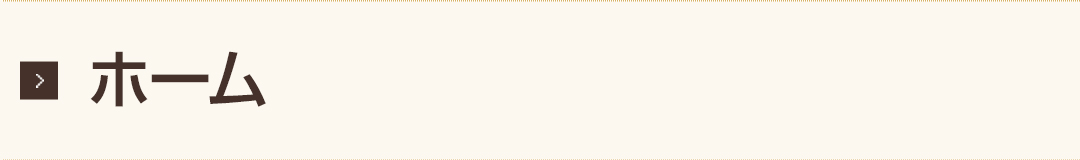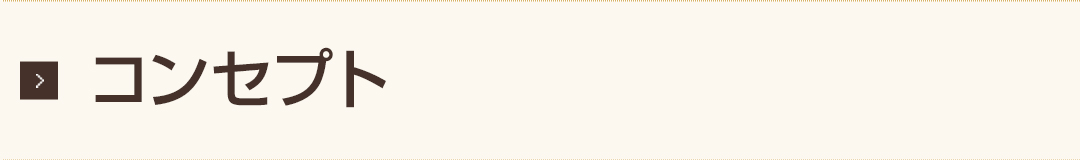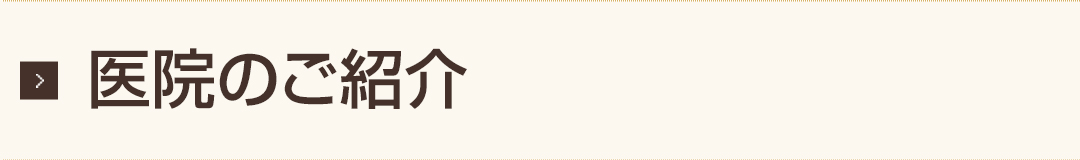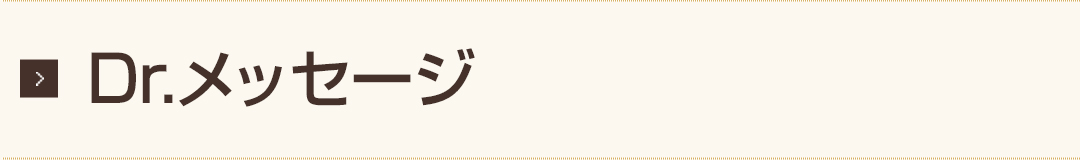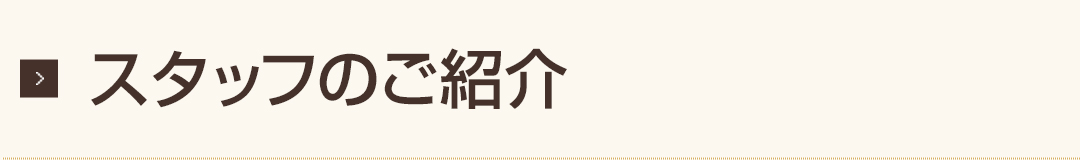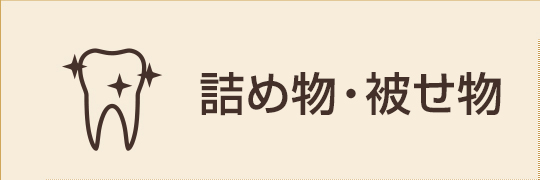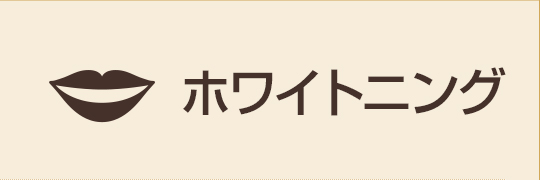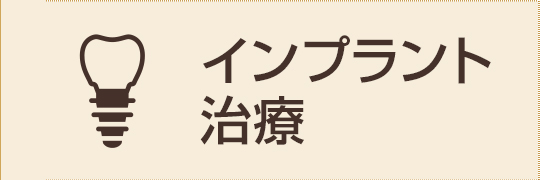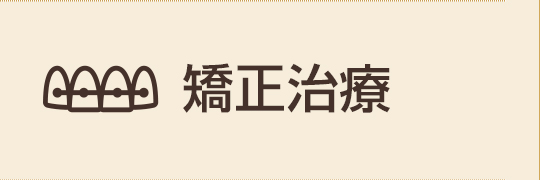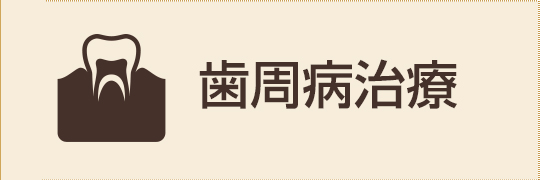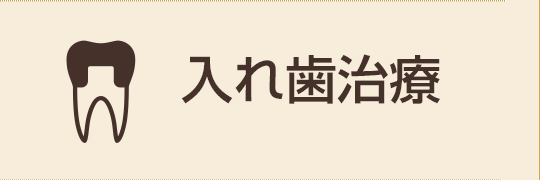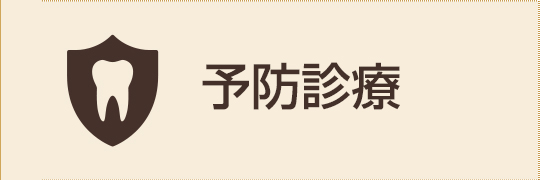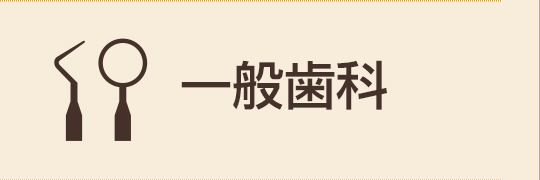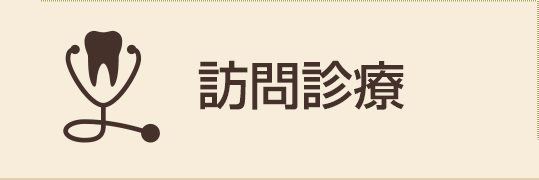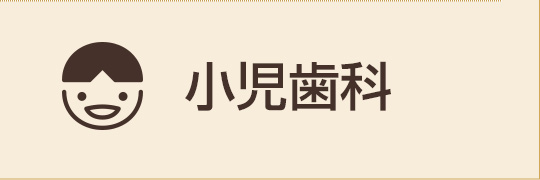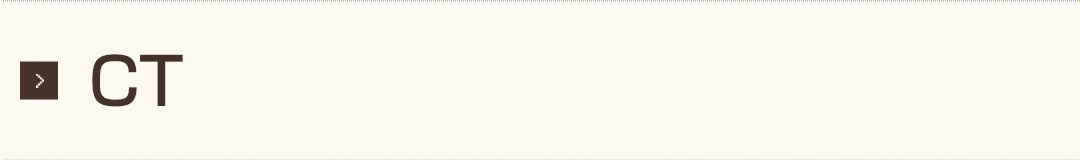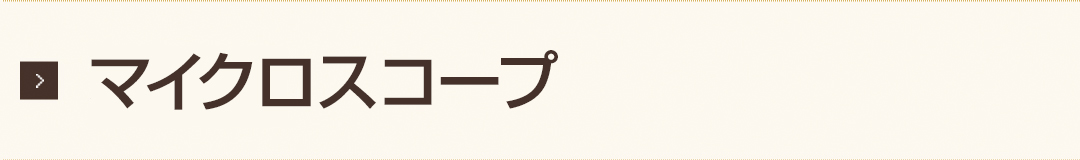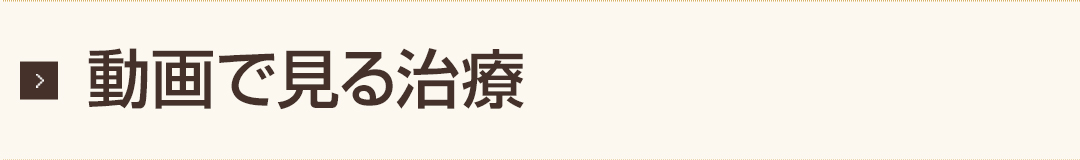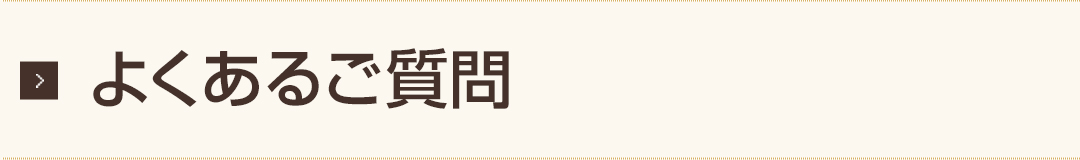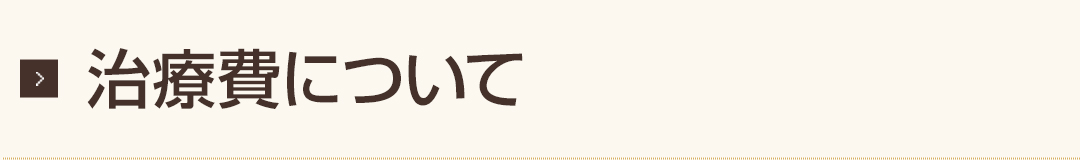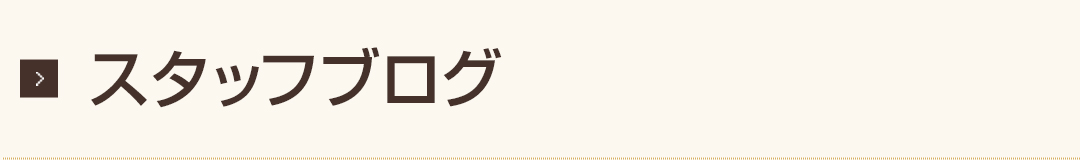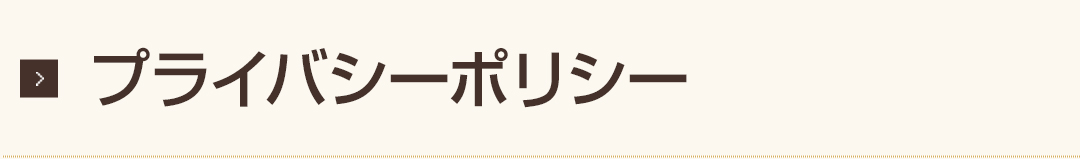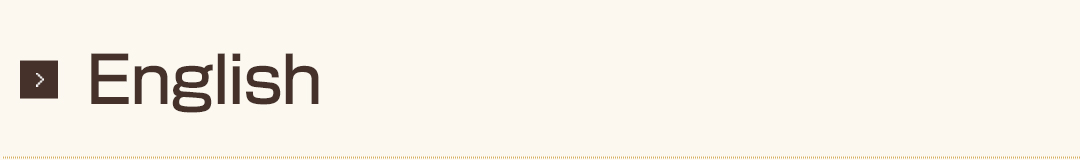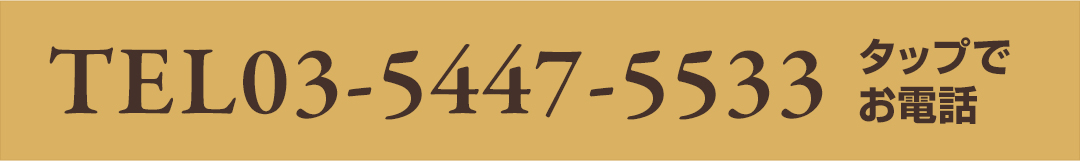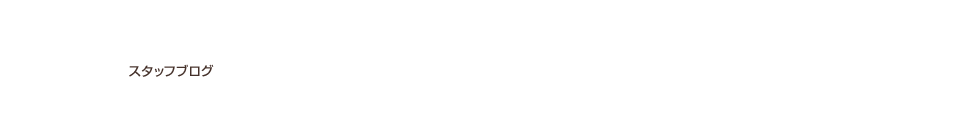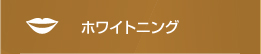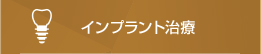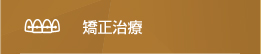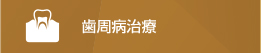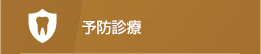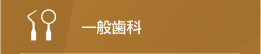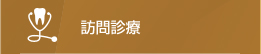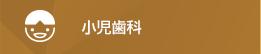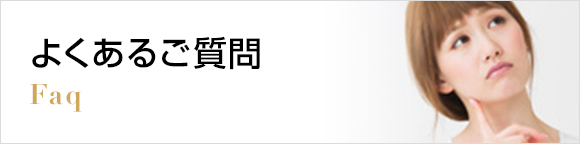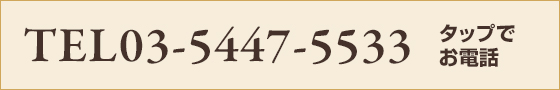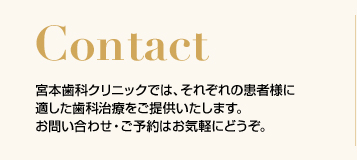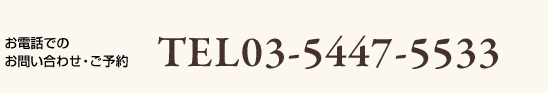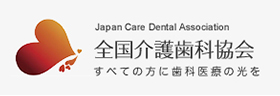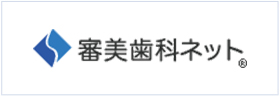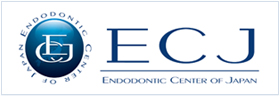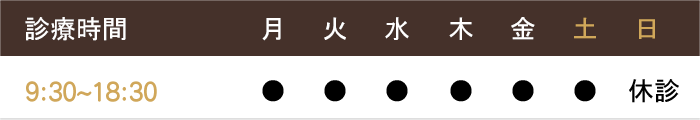フッ素の3つの働きとは?むし歯予防に欠かせない理由
2025/05/07
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、むし歯予防に欠かせない「フッ素」の働きについてご紹介します。
フッ素とは
みなさんは、歯科医院や歯みがき粉などでよく目にする「フッ素」について、どんな働きがあるかご存知でしょうか?フッ素は、むし歯予防にとても効果的な成分であり、歯科医療の現場では長年にわたって活用されています。特に子どもから大人まで、幅広い年齢層で取り入れたい予防手段のひとつです。
① 歯を強くする「再石灰化の促進」
私たちの歯は、食事や飲み物を摂るたびに、酸によって表面のエナメル質が少しずつ溶けています。これを「脱灰」といいます。しかし、唾液の働きによって、失われた成分が再び歯に取り込まれ、修復される「再石灰化」というプロセスも自然に起こっています。ここで重要なのがフッ素の存在です。
フッ素は、この再石灰化を助ける作用があります。フッ素が歯に取り込まれることで、エナメル質がより硬く、酸に強い状態に修復されやすくなるのです。これによりむし歯の進行を防ぐだけでなく、初期のむし歯であれば自然に回復する可能性も高まります。
② むし歯菌の活動を抑える「抗菌作用」
むし歯の原因となるのは、「ミュータンス菌」などの細菌が糖を分解して酸をつくり、その酸が歯を溶かすことにあります。フッ素には、むし歯菌の活動を抑える抗菌作用があります。具体的には、フッ素がむし歯菌の代謝を抑制することで、酸の産生量を減少させます。酸が減れば歯が溶けるリスクも下がるため、むし歯の予防につながるのです。このようにフッ素は、歯を守るだけでなく、むし歯の原因そのものにも働きかける優れた成分です。
③ 歯質を強化して「むし歯に強い歯をつくる」
歯の表面は主に「ハイドロキシアパタイト」という成分からできています。これ自体は酸に弱く、むし歯になりやすい構造です。しかし、フッ素が歯に取り込まれると、「フルオロアパタイト」という構造に変わります。これは、酸に強く溶けにくい性質をもつため、むし歯に対する耐性が高くなります。
つまり、フッ素は歯を「むし歯になりにくい状態」に変えてくれるのです。特に、生えたばかりの永久歯や乳歯は柔らかくむし歯になりやすい時期なので、フッ素による予防はとても有効です。
まとめ
今回ご紹介したように、フッ素にはむし歯予防に欠かせない3つの働きがあります。そして、毎日のケアにフッ素を取り入れることでむし歯を防ぎ、歯を健康に保つことができます。フッ素の活用方法は次回以降のブログでご紹介します。
Category - MIミニマムインターベーション