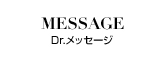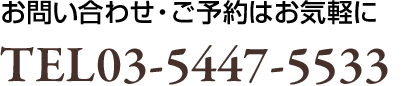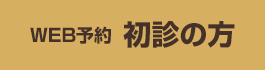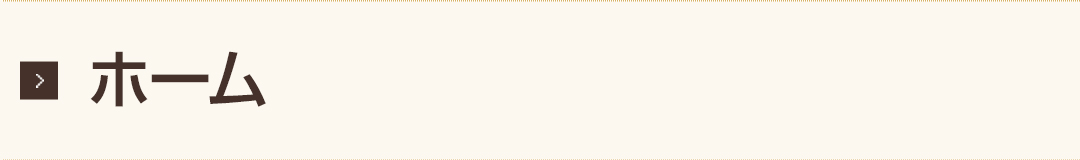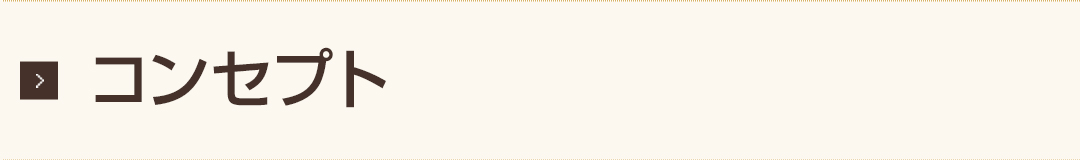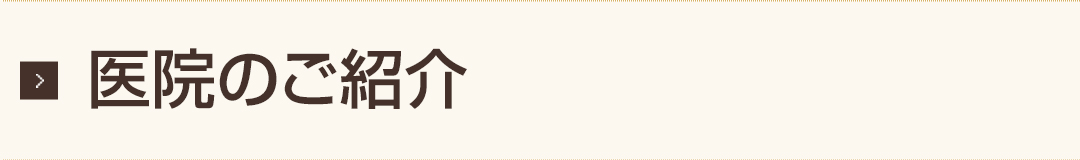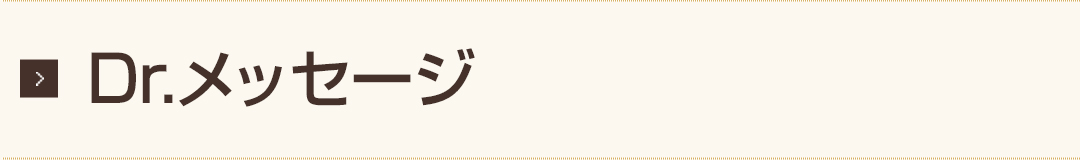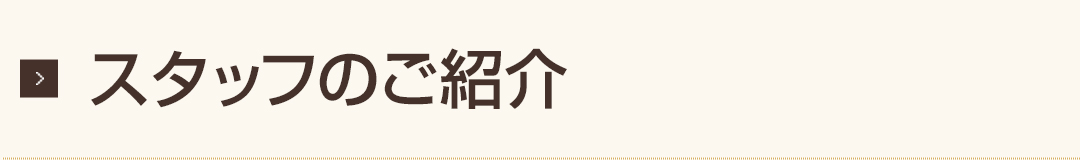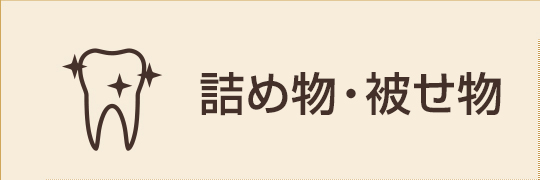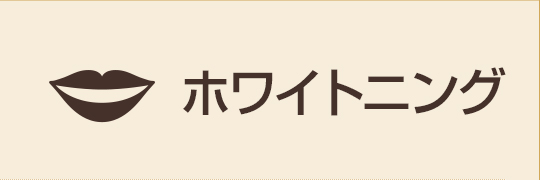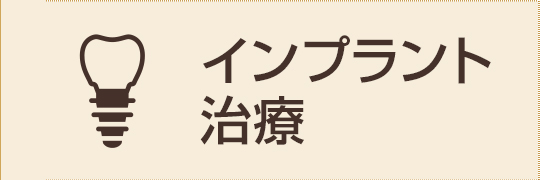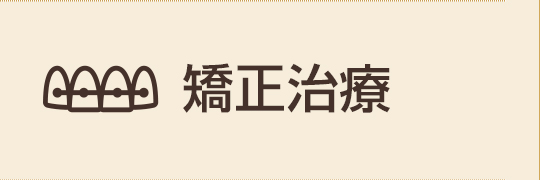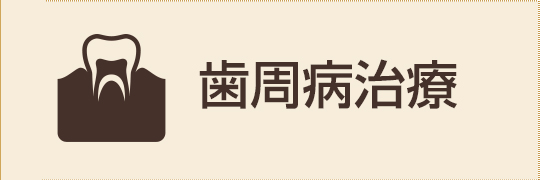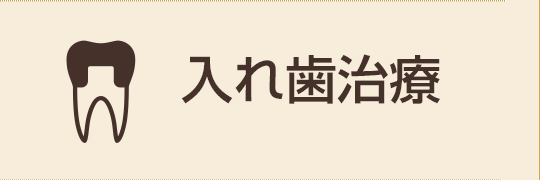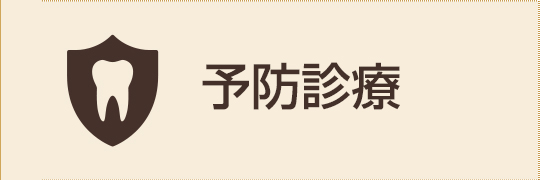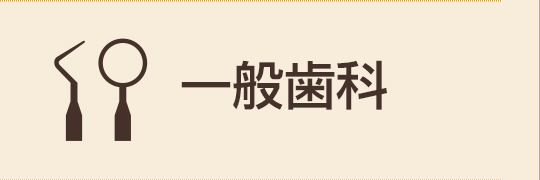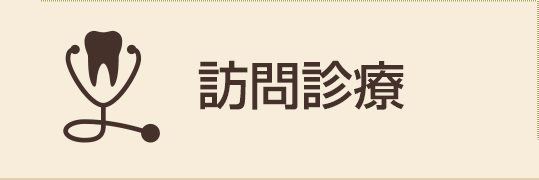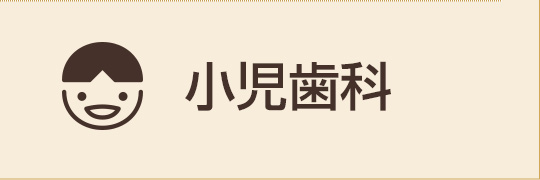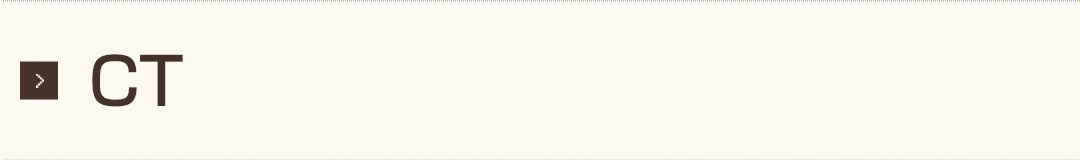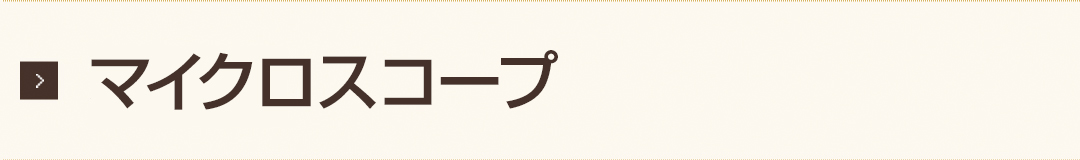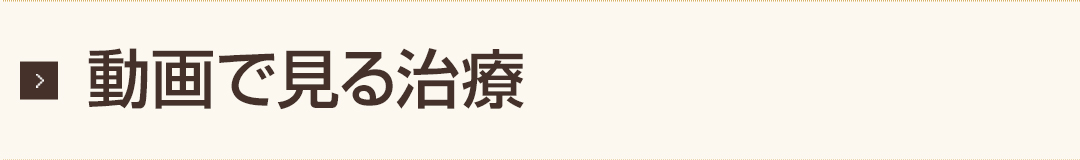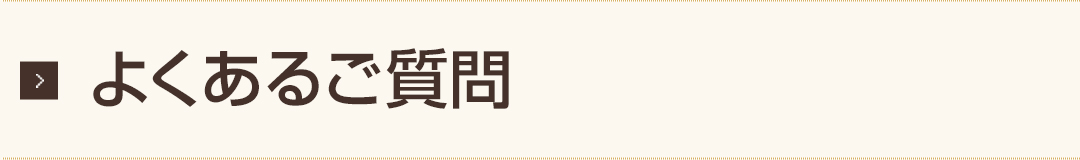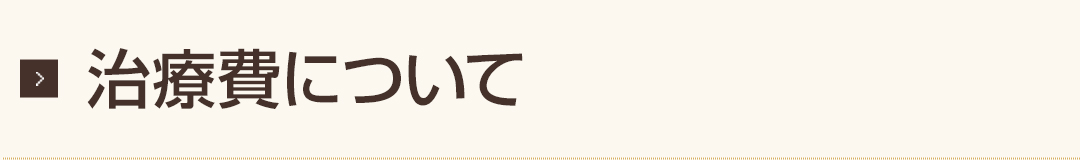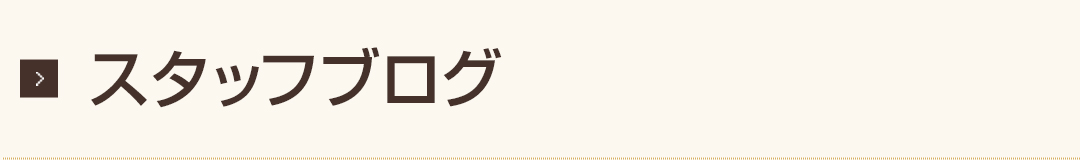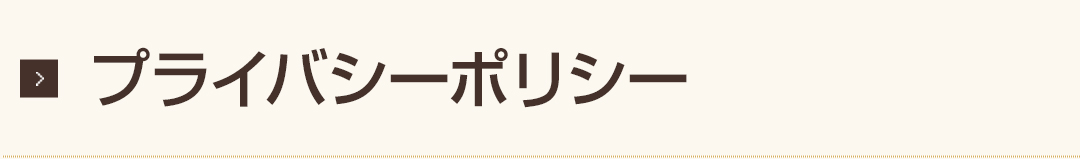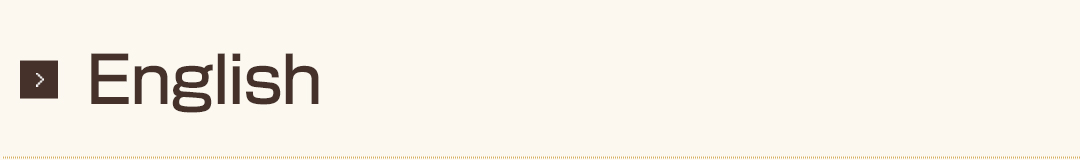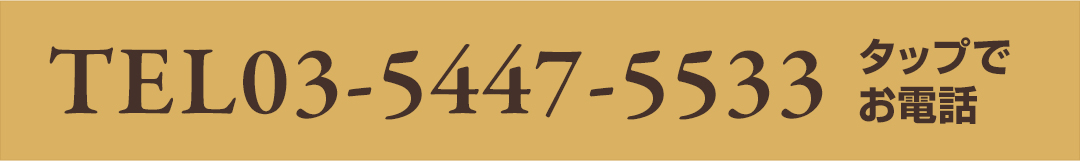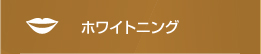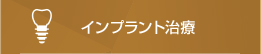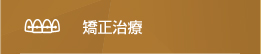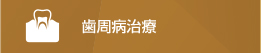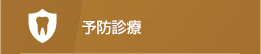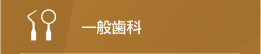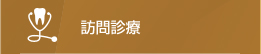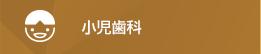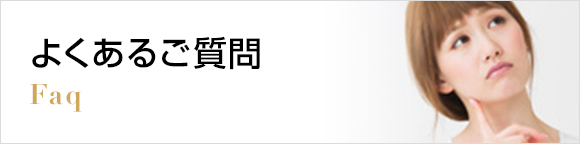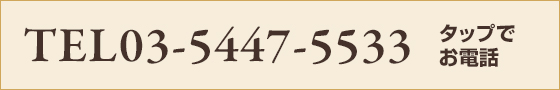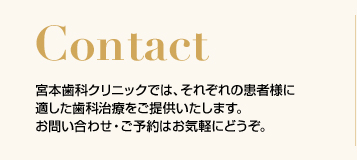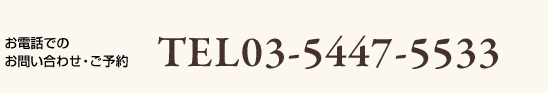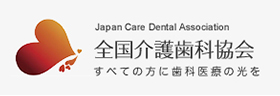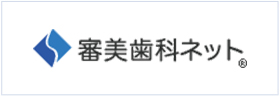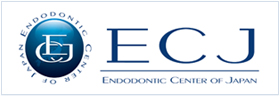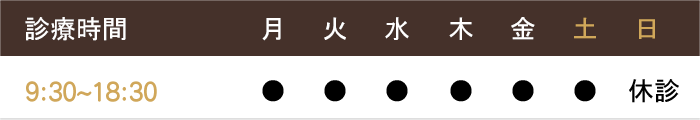意外と知らないホワイトニングの歴史
2023/04/05
近頃ではすっかり身近になったホワイトニングですが、その始まりは意外に古く、100年以上前にまでさかのぼります。今回は、意外と知らないホワイトニングの歴史についてご紹介します。
「歯を白くすること」の始まり
ホワイトニングというワードが初めてアメリカの歯科雑誌に掲載されたのは、1844年のことでした。当時でいうホワイトニングは、ミョウバンで歯の着色を落とし、歯を白くするという方法でした。その後、次亜塩素酸ナトリウムやシュウ酸などが試されてきましたが、現在と同じ過酸化水素を使用したホワイトニング方法が登場したのは、初めて雑誌に掲載されてから5年後の1889年のことです。その後、1918年に日光浴をしていた歯科医師により、過酸化水素に光を当てることによって歯を白くする方法が発見されました。これがオフィスホワイトニングの始まりです。
ホワイトニングの普及と発展
時は流れ1968年、過酸化尿素を用いたホームホワイトニングの原形ともいえるものが誕生しました。実用化に至ったのは少し先の1989年ごろで、歯肉炎の治療に使用する過酸化尿素が歯を白くする作用をもつことを偶然発見したことがきっかけです。短期間で歯を白くするための様々な研究が繰り返され、世界初のホームホワイトニング剤「White&Brite」が、1991年にオフィスホワイトニング剤「Hi-Lite」が発売されました。現在では、世界で100種類以上ものホワイトニング剤が発売されています。
日本におけるホワイトニングの普及
日本においては、1998年にオフィスホワイトニング剤が初めて厚生労働省に認可されました。もともと日本には「お歯黒」の文化があったこともあり、すぐにはホワイトニングは広まりませんでしたが、1990年代の終わりに美白ブームが到来したことや、「芸能人は歯が命」のキャッチフレーズで有名なCMが放映された影響もあり、次第に人々に認知されるようになります。その後、歯科医院での施術だけでなくホワイトニングを専門とした店舗が登場するようになり、ホワイトニングは人々にとって身近なものとなりました。
今回は、ホワイトニングの歴史についてご紹介しました。
最近では脱マスクに向けて歯の色を白くしたい、というご依頼も増えてきています。
当院ではより効果的に白い歯を目指せるホワイトエッセンスを導入しておりますので、ホワイトニングをご希望の方はお気軽にご相談ください。
治療後に気をつけたいインプラント周囲炎
2023/03/31
今回は、インプラント治療後に気をつけたいインプラント周囲炎についてご紹介します。
インプラントは一度入れたらそれで終わり、ではありません。毎日のご自身でのセルフケアや、歯科医院での定期的なメンテナンスを怠ると、最悪の場合インプラントが抜け落ちてしまうことにもなりかねません。
インプラント周囲炎とは
インプラント周囲炎とは、インプラントまわりの組織が歯周病のような状態になってしまうことを指します。インプラントは天然歯よりも炎症に対する抵抗力が弱いため、細菌に感染すると一気に骨吸収が進行してしまうのです。骨吸収が進むとインプラントを支える骨が破壊されるため、支えを失ったインプラントは抜け落ちてしまいます。自覚症状が出にくいため、気が付かないうちに重症化してしまうケースも多いため、メンテナンスによる予防が非常に重要となります。
インプラント周囲炎の原因
インプラント周囲炎は歯周病原菌の繁殖によって生じます。プラーク(歯垢)がインプラントに付着したまま放置されると、そこから細菌が繁殖して歯ぐきや歯を支える骨に影響を与えるのです。また、これだけでなく、糖尿病や貧血などの全身疾患や喫煙などの生活習慣も、インプラント周囲炎を引き起こす原因となる可能性があります。
インプラント周囲炎の予防法3つ
・毎日の丁寧なセルフケア
日々の丁寧な歯磨きこそが、インプラント周囲炎の予防への第一歩です。インプラントに付着したプラーク(歯垢)は毎日しっかり除去し、お口の中を清潔に保ちましょう。歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシなどの補助清掃用具を活用することも大切です。
・定期的な歯科医院でのメンテナンス
ご自身でのセルフケアでは落とし切れない汚れは、歯科医院でのクリーニングで除去します。メンテナンスでは、汚れの確認のほか、歯ぐきや顎の骨の状態や噛み合わせについても診査を行い、必要に応じて処置をいたします。
・禁煙などの生活習慣の見直し
インプラント周囲炎は全身の病気や喫煙などの生活習慣とも大きな関わりがあります。インプラントを守るためにも、生活習慣を見直して規則正しい生活を心がけましょう。
まとめ
インプラントを長く使い続けるためには、ほかの歯と同じように毎日のセルフケアや定期的なメンテナンスが欠かせません。インプラント周囲炎を予防し、お口の健康を守りましょう。インプラント治療後のメンテナンスはお気軽に当院までご相談ください。
ホワイトニングの効果をできるだけ長持ちさせるメンテナンス
2023/03/29
ホワイトニングで理想の白さの歯を手に入れたら、できるだけ効果を持続させたいですよね。
今回は、ホワイトニングの効果をできるだけ長持ちさせるメンテナンスについてご紹介します。
ホワイトニングは定期的なメンテナンスが大切
ホワイトニングで手に入れた白さを維持するには、定期的なメンテナンスが欠かせません。歯は、生活習慣や再石灰化の影響でどうしても徐々に色戻りしてしまいます。そのため、定期的にホワイトニングを続けることで、色戻りを防ぎやすくなります。ホワイトエッセンスでは、オフィスホワイトニングの場合は3ヶ月に1回程度、ホームホワイトニングの場合は2週間に1回程度のメンテナンスが推奨されています。オフィスホワイトニングでのメンテナンスは、30分の処置時間で完了します。気軽にご来院いただけますので、ぜひご活用ください。
ホワイトニング効果のある歯磨き粉を使う
毎日のセルフケアにホワイトニング効果のある歯磨き粉を取り入れることも、ホワイトニング効果を持続させるための方法の一つです。歯磨き粉は、研磨剤があまり含まれていないものがおすすめです。研磨剤の粒子が大きすぎると、かえって歯のエナメル質を傷つけてしまう可能性があるからです。市販のホワイトニング歯磨き粉を選ぶときには、低研磨もしくは研磨剤不使用と表示のあるものを選ぶとよいでしょう。
色の濃い食べ物や飲み物には気をつける
ホワイトエッセンスは一般的なホワイトニングに比べて食事制限はほとんどありませんが、日常生活の中で色の濃い食べ物や飲み物に少し気をつけるだけでも色戻りを防ぐことができます。一見、着色には関係なさそうですが意外と歯の色に影響があるのが大豆製品です。見た目の色も薄いため問題なさそうですが、大豆に含まれるイソフラボンはポリフェノールの一種であるため、歯の表面のタンパク質と結合し黄ばみに繋がる可能性があります。このような食品を食べた後は、より丁寧に歯磨きをしましょう。
当院で導入しているホワイトエッセンスは、一般的なホワイトニングに比べて薬剤の漂白効果も高く、ホワイトニング後の食事制限もほとんどありません。メンテナンスにかかる時間も30分と短く、お忙しい方でも気軽にご来院いただけます。ホワイトエッセンスにご興味のある方は、お気軽に当院までご相談ください。
意外と知らないインプラントの歴史
2023/03/24
今回は、意外と知られていないインプラントの歴史ついてご紹介します。
インプラントは、医療機器を体内に埋め込む治療や材料の総称で、歯科だけでなく整形外科や美容外科など他の医療分野においても広く用いられます。歯科でのインプラント治療が広く普及してきたため「インプラント」で通ずるようになっていますが、本来は「デンタルインプラント」が正式な名称です。
では、この「デンタルインプラント」はどのような歴史や背景をもつ治療方法なのでしょうか?
インプラントのはじまり
インプラントは新しい治療法、というイメージをお持ちの方も多くいらっしゃるかと思いますが、はじまりは紀元前にまで遡るといわれています。インカ文明でミイラからサファイアで作られた人工的な歯根が発見されたことや、エジプト文明で宝石などを歯が抜けた場所に埋めた跡が見つかったことなどが根拠です。インプラントは、私たちが思っているよりもずっと昔から歯を失ったあとの治療として行われてきたようです。
インプラント治療の発展
はじめて「インプラント」という治療の名称が用いられたのは、1885年にアメリカのヤンガー氏が人工歯を歯槽骨に移植する手術を行ったときといわれています。その後、1952年にスウェーデンのブローネマルク氏による偶然の発見が、インプラント治療を大きく発展させることとなります。
ブローネマルク氏が発見したのは、骨とチタンが結合するということでした。それまで、インプラントの素材には宝石や貝殻、人や動物の歯、骨などありとあらゆるものが先人たちにより試されてきましたが、骨と結合しない、身体に馴染まない、といった課題があったのです。この画期的な発見により、チタンが生体親和性が高く、骨としっかり結合できる素材であるということが示され、インプラント治療の急速な発展のきっかけとなりました。その後、インプラントの素材や形などの研究が進み、1965年に初めてチタン製インプラントが実際の臨床の現場で使われました。
日本におけるインプラント治療
日本におけるインプラント治療の歴史は、大阪歯科大学の河原氏らにより1978年から始まります。このときはまだ人工サファイア製素材を用いた手術で、チタン製のインプラントが使用されるようになったのは1983年頃です。それ以降、試行錯誤を繰り返し、様々な課題を乗り越えながら、安心で安全な治療方法へと発展し、現在に至ります。
今回は、インプラントの歴史についてご紹介しました。
インプラントは日本でも40年以上の歴史がある治療方法であり、その成功率も97%以上と高い信頼性・安全性を誇る治療方法です。
当院ではインプラントにも力を入れており、豊富な知識と経験で治療にあたっています。インプラントにご興味のある方は、ぜひ当院までお気軽にご相談ください。
ホワイトニング後の食事制限が心配な方こそ、ホワイトエッセンスがおすすめです
2023/03/22
せっかくホワイトニングをしたからには、効果を最大限保ちたいですよね。そのためには、ホワイトニング後に食事や飲み物の制限が必要だと聞いたことのある方もいらっしゃるかと思います。
今回は、ホワイトニング後の食事制限が心配な方にホワイトエッセンスをおすすめする李雄についてお話ししていきます。
一般的なホワイトニング後に控えたほうがよい食べ物・飲み物5選
一般的なホワイトニングでは、ホワイトニング施術後30分の飲食厳禁に加え、オフィスホワイトニングの場合は施術から24時間、ホームホワイトニングの場合は施術から2~3時間は飲食の内容に気をつける必要があります。特に、オフィスホワイトニングで使用する薬剤は濃度が高く即効性がある一方で後戻りしやすいため、施術後の食事に気をつける時間も長くなります。
色の濃い食べ物
ホワイトニング後は歯の表面に色素が着色しやすい状態になっています。したがって、色の濃い調味料(醤油、味噌、ケチャップ、ソースなど)やそれらを使用したもの(カレー、ピザ、トマトソースのパスタ、ビーフシチュー、ハンバーグなど)は控えましょう。ほうれん草やいちごなどの色素の濃い野菜・果物にも注意が必要です。
色の濃い飲み物
これはイメージがつきやすいかもしれませんが、コーヒーや緑茶など、着色しやすい飲み物も控えましょう。
ポリフェノールを多く含む食べ物や飲み物
赤ワイン、チョコレート、ぶどうなど、ポリフェノールを多く含む食品も、着色しやすいため控えましょう。
イソフラボンを含む食べ物や飲み物
豆腐や豆乳などは色も白く、一見問題なさそうに見えますが実は注意が必要です。豆腐や豆乳に含まれるイソフラボンは、ポリフェノールの一種で着色の原因となる可能性があります。
酸性度の高い食べ物や飲み物
レモンやみかんなどの柑橘類、炭酸飲料、スポーツドリンクのような酸性度の高い食品・飲料も、歯に刺激が伝わりやすいため避けた方がよいでしょう。
ホワイトエッセンスの飲食制限
ホワイトニングで使用する薬剤により、歯の表面のペリクルという膜が剥がれます。ペリクルは唾液に含まれる成分から構成されており、歯の表面をコーティングするような役割をもっているため、これが剥がれることで色素沈着しやすくなってしまいます。そのため、施術後の30分のみは飲食をお控えいただいております。
ホワイトエッセンスであれば、それ以降の食事制限はありません。着色を気にせず、お好きなものをお召し上がりいただけます。
以上のように、ホワイトニング後の食事制限が心配な方にはホワイトエッセンスがおすすめです。ご興味のある方は、ぜひお気軽に当院までご相談ください。