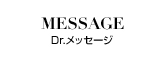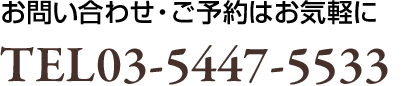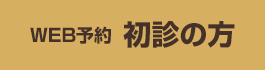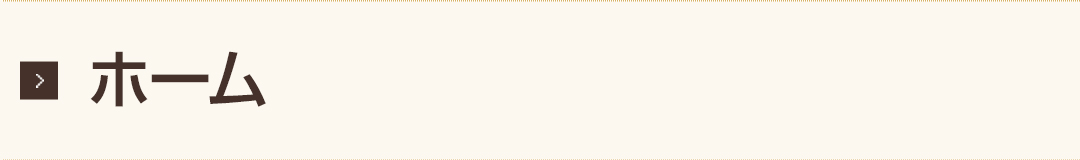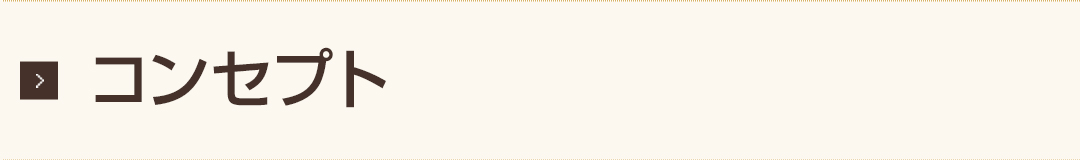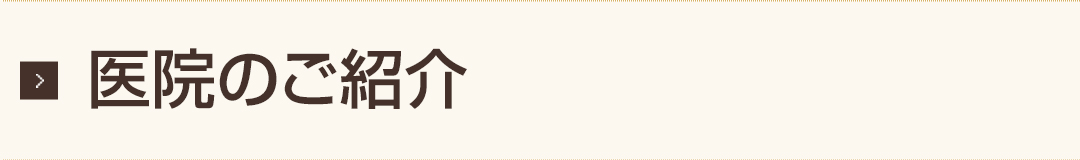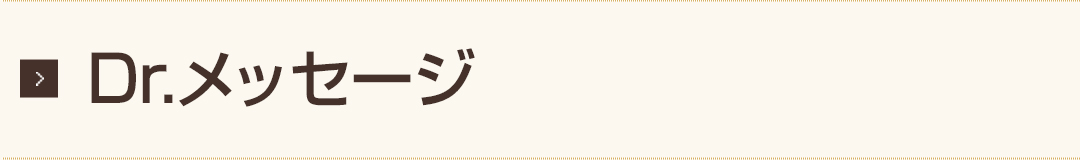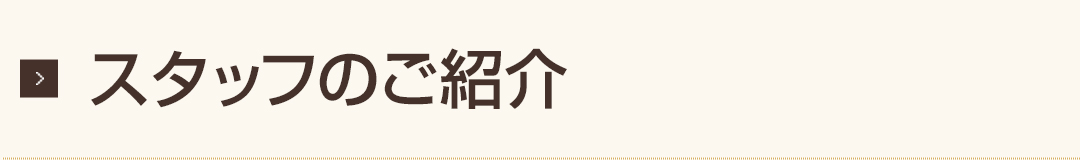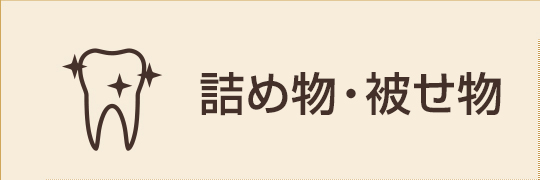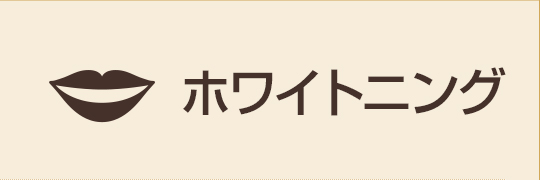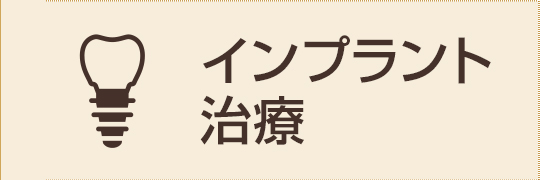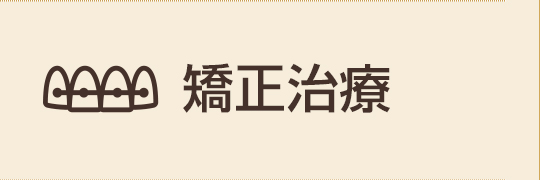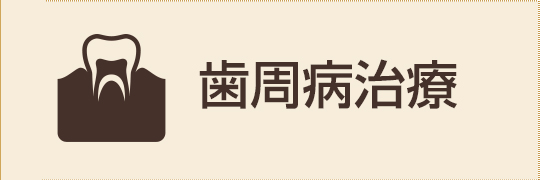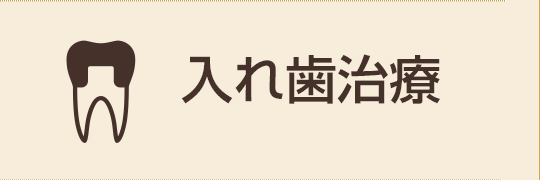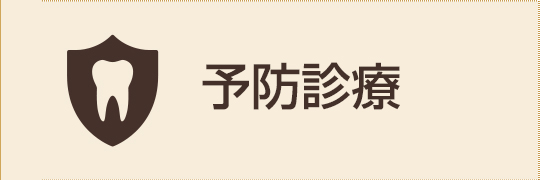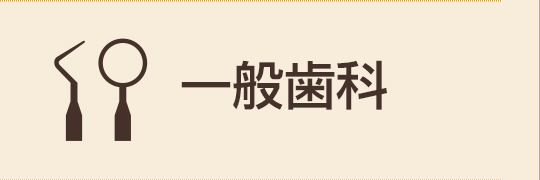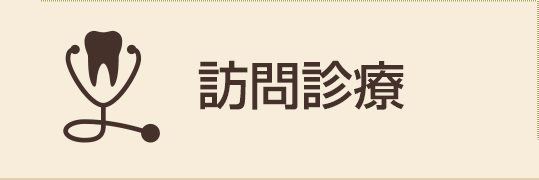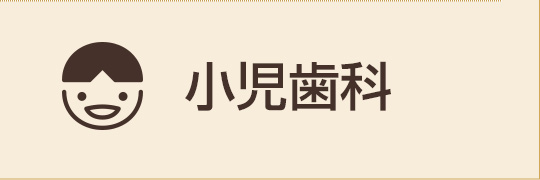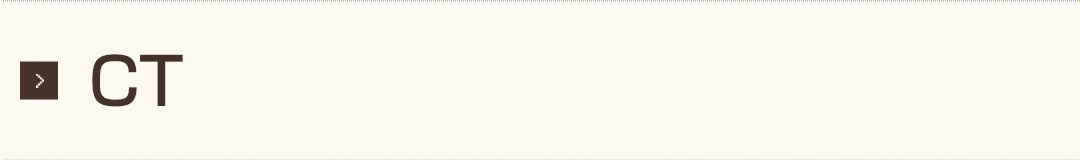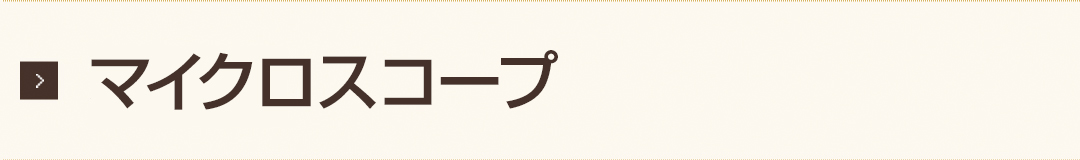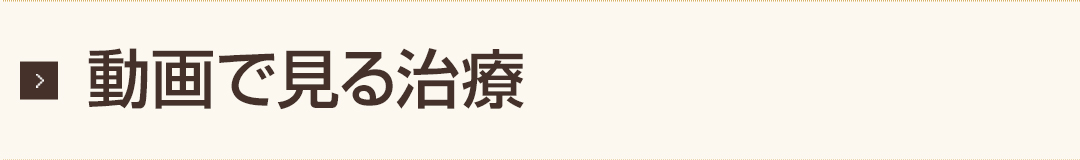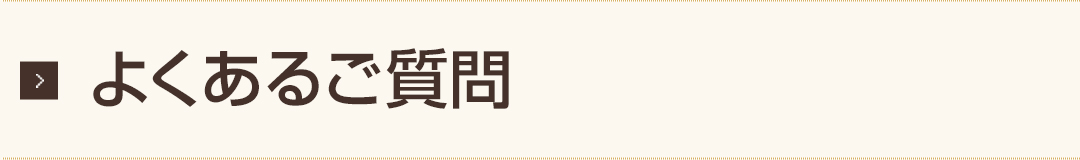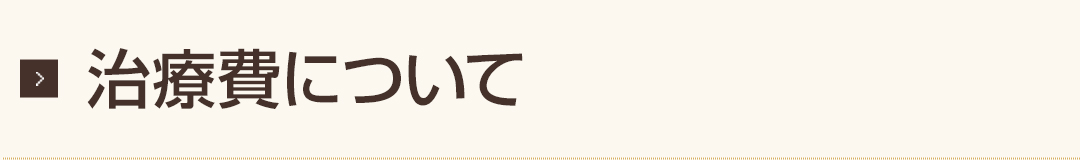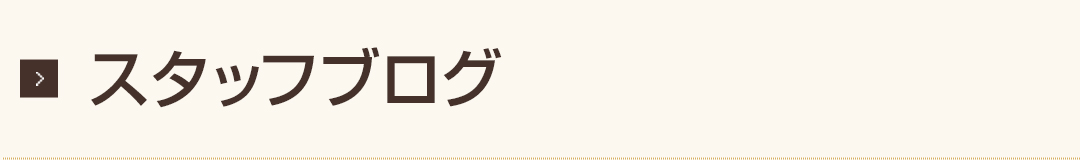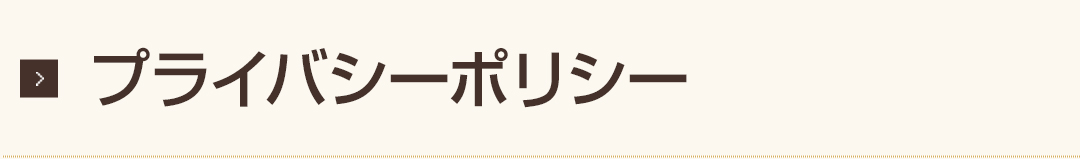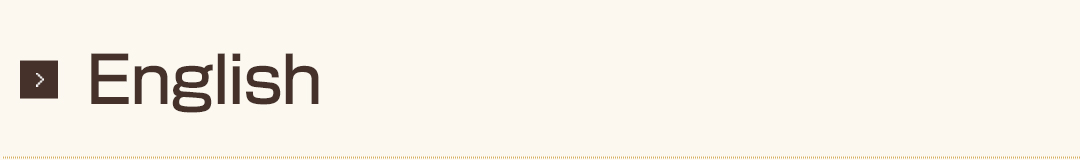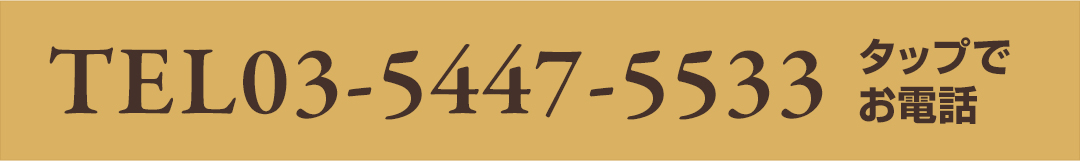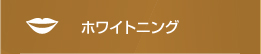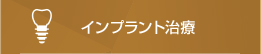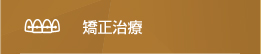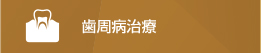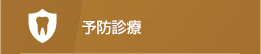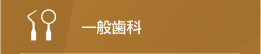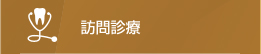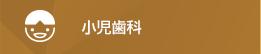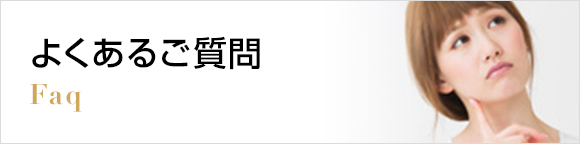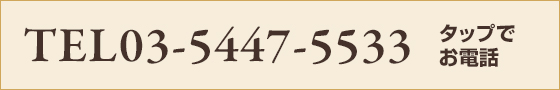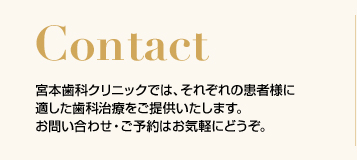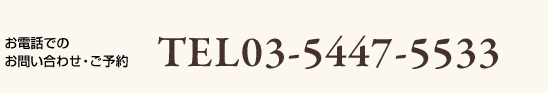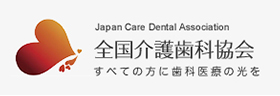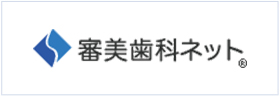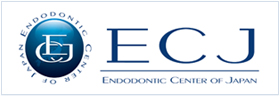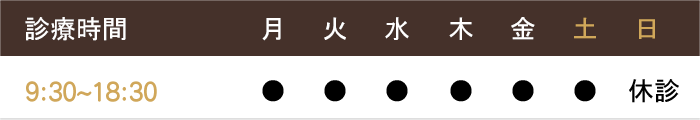ダイレクトボンディングとはどのような治療方法?
2024/04/22
今回は、ダイレクトボンディングの概要についてご紹介します。むし歯の治療をする際には、むし歯になっている歯質を削ったあとに何かしらの方法で修復する必要があります。その選択肢の一つに「ダイレクトボンディング」とよばれるものがありますが、どのような治療方法かご存じですか?
ダイレクトボンディングとは
ハイブリッド樹脂を用いて歯の形態を修復し、むし歯により失われたエナメル質や象牙質を補う方法を「ダイレクトボンディング」といいます。歯科治療における「ボンディング」とは、高分子の材料を歯質に「接着」するためのステップのことです。歯と修復材料を直接化学的・物理的に接着させ、一体化する技術を応用しています。この修復方法では歯を削る量を最小限に抑えられるだけでなく、色調や透明感の異なる素材をいくつも重ねていくため、天然歯のような透明感のある仕上がりが可能です。
ダイレクトボンディングの歴史
ボンディングの技術は、歯科業界においても長い歴史をもちます。1960年当時、歯を修復する方法としては金属製のクラウンやブリッジが一般的でしたが、金属の見た目の悪さなどから白い材料を用いた修復方法が研究されるようになりました。しかし、はじめのうちは修復に用いられたコンポジットレジン(樹脂)が詰めてもすぐに取れてしまう、レジンと歯の隙間からむし歯が再発してしまうなどの課題があったといわれています。その後、1977年に日本の歯科材料メーカーから歯のエナメル質と象牙質の双方に接着する特性をもつ修復材料が開発され、徐々にこの方法が普及しました。
ダイレクトボンディングの原理
ダイレクトボンディングにおける接着は、いくつかのステップにより行われます。
1.酸処理
まず、歯の表面のエナメル質を酸処理して部分的に脱灰させます。表面を粗造にして接着剤が剥がれにくいようにします。
2.プライミング
酸処理によってできた表面の凹凸部分に、プライマーとよばれる表面処理剤を流し込み、このあとの接着がしやすい状態にします。
3.ボンディング
ボンディング材を塗布して光硬化させることで、歯質と接着させます。この上に樹脂を盛っていくと樹脂がボンディング材と化学結合するため、隙間からむし歯になったり樹脂がすぐに取れてしまうようなことはありません。
まとめ
今回は、ダイレクトボンディングの概要についてご紹介しました。ダイレクトボンディングはミニマルインターベンションの考え方に基づいた治療方法の一つでもあり、歯を修復する際の選択肢としてもおすすめです(ただし全ての症例に適応できるとは限りません)。
当院では患者様のお口の中の状況に合わせた治療方法をご提案いたしますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
歯をなるべく削らない治療とは?基本的な理念を解説します
2024/04/19
今回は、歯をなるべく削らない治療「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方についてご紹介します。これまでのむし歯治療というと、むし歯になった部分の歯を削ったり神経をとる治療が一般的でした。しかし、近年は「なるべく歯を削らない、できるだけ神経を残す」という考え方が広まりつつあります。
ミニマルインターベンション(MI)とは
むし歯の管理において介入を最小限にしようという考え方を「ミニマルインターベンション(Minimal Intervention)」といいます。ミニマルインターベンションにおいては、「むし歯の管理においてできるだけ歯質や神経を犠牲にせずに治療をする」ということを基本理念としています。
ミニマルインターベンションの誕生
それまで「むし歯になったら歯を削る、神経をとる」という治療方法が当たり前だった歯科業界において、大きな変化が起きたのは2000年のことです。2000年にオーストリアのウィーンで行われた国際歯科連盟(FDI)において、「Minimal Intervention in the Management of Dental Caries」が採択されました。これがミニマルインターベンションの始まりです。
ミニマルインターベンションの考え方
2000年のFDIにおいて採択された理念の中では、むし歯治療のマネージメントとして以下の5つの項目が挙げられています。
- お口の中の細菌叢の改善
- 患者さまに対する指導・教育
- エナメル質および象牙質に限局したむし歯で、まだ齲窩(むし歯の穴)を形成していないむし歯に対する再石灰化の促進
- 齲窩を形成したむし歯に対する最小限の切削
- 欠陥のある詰め物や被せ物の補修
このように、むし歯の治療に対する考え方の中で初めて「最小限の切削」という言葉が登場したのです。ミニマルインターベンションというと「歯を削らない」という点がクローズアップされがちですが、これはミニマルインターベンションにおける概念のうちの一部であるということを知っておきましょう。
まとめ
今回は、歯をなるべく削らない治療「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方についてご紹介しました。むし歯の治療方法は年々進化を遂げてはいますが、まずはむし歯にならないことが何よりも大切です。毎日の丁寧なセルフケアと定期的な歯科医院の受診でむし歯を予防しましょう。
当院ではミニマルインターベンション(MI)の考え方に基づき、患者さまお一人おひとりにとって最善の治療方法をご提案しております。ご予約、お問合せはお電話で承っております。
ホワイトニング後も気をつけたい むし歯の予防
2024/04/17
今回は、むし歯の予防についてご紹介します。ホワイトニングの処置を受ける前には必ずむし歯がないか確認を受けることをおすすめしており、またホワイトニング後もむし歯を予防することはお口の健康を守るためにも大切です。
ホワイトニング後にも大切なむし歯予防
せっかくホワイトニングで白い歯を手に入れたならば、その後もむし歯にならないように予防することが大切です。むし歯の治療に使われるプラスチックなどの素材はホワイトニングをしても白くならないだけでなく、時間の経過とともに劣化する可能性もあるため、歯が部分的に違う色に見えてしまうこともあります。むし歯の原因の一つでもあるプラークは、歯が黄ばんで見える原因にもなるため、プラークをしっかり除去することはホワイトニング効果を長持ちさせることにも繋がるでしょう。
むし歯を予防するには
以下のことを実践することで、効果的にむし歯を予防しましょう。
- 毎日のセルフケアを丁寧に行う
プラークを確実に除去するためには、まず毎日の歯磨きをはじめとしたセルフケアを丁寧に行うことが大切です。歯ブラシで磨くだけではお口の中のプラークの6割ほどしか除去できないといわれています。歯ブラシで磨くことに加え、デンタルフロスや歯間ブラシ、ワンタフトブラシなどの補助清掃用具も活用するとよいでしょう。
- 定期的に歯科医院でメンテナンスや検診を受ける
いくらセルフケアを丁寧に行ったとしても、どうしても落としきれないプラークや汚れは存在します。ホワイトニングのメンテナンスと同時にクリーニングや検診も受け、お口の中の状態をチェックしてもらいましょう。ホワイトエッセンスでは独自の「ウルトラファインバブル」の技術を用いたクリーニングを実施しており、効率よく確実にバイオフィルムを除去できます。
- フッ素を活用する
むし歯予防に効果的なものとして、フッ素の活用も挙げられます。フッ素は歯磨き粉などにも含まれている成分ですが、歯科医院で「フッ素塗布」として処置を受けることも可能です。フッ素の働きや効果については、次回以降のブログで詳しくご紹介します。
- 規則正しい食生活をする
1日中ずっと飲食をしているとお口の中が常に酸性に傾き、むし歯になりやすい状態になってしまいます。食事や間食は時間や回数を決めて規則正しい食生活を心がけましょう。
まとめ
今回は、むし歯の予防についてご紹介しました。ホワイトニング後も毎日のセルフケアと定期的な歯科医院の受診でむし歯を予防しましょう。
当院は、多数の症例実績を誇るホワイトエッセンス加盟医院です。ホワイトニングのご予約、お問合せはお電話で承っております。
レントゲン検査の被ばく量
2024/04/12
今回は、インプラント検査の被ばく量についてご紹介します。
インプラント治療は、顎の骨の中にインプラント体(人工歯根)を埋入し、その上から上部構造(人工歯)を被せる手術です。外から見ただけの情報だけでは手術に必要な情報が十分に得られないため、レントゲンによる検査で得られる情報が非常に重要になってきます。レントゲンと聞くと被ばく量が心配な方もいらっしゃいますが、それぞれの検査での被ばく量はどの程度なのでしょうか。
何もしていなくても被ばくする「自然被ばく量」とは?
私たちが放射線による被ばくを受けるのには、自然界から受けるものと人工的に受けるものの2種類があります。前者は、空気中や大地、宇宙、食物から受けるもののほか、飛行機に乗ったときに受けるものもあります。後者については、医科および歯科におけるレントゲン検査などです。日常生活を送る中で何もしていなくても放射線を受けていることを「自然被ばく」といいます。年間に受ける自然被ばく量を合計すると世界平均で2.4ミリシーベルトといわれており、日本においては平均1.5~2.1ミリシーベルトです。
各レントゲンにおける被ばく量
では、人工放射線による被ばく量はどの程度なのでしょうか。
・パノラマレントゲン…約0.03ミリシーベルト(1回あたり)
・デンタルレントゲン…約0,01ミリシーベルト(1回あたり)
・歯科用CT…0.1ミリシーベルト(1回あたり)
このように、歯科におけるレントゲン検査で受ける被ばく量は、非常に少ないものです。人体に影響が及ぶ被ばく量は100シーベルト以上といわれているため、自然被ばく量に加えてレントゲン撮影を行ったとしても、数値としては人体に影響を及ぼすようなことはほぼありません。さらに、レントゲンを撮影するときに歯放射線用の防護エプロンをつけて撮影を行うことがほとんどです。このエプロンをつけることで、レントゲン検査によって受ける被ばく量は限りなくゼロに近くなります。
まとめ
今回は、各レントゲン検査の被ばく量についてご紹介しました。インプラントの治療を始める前には、適切な
検査を行うことが正しい診断、治療の成功に繋がります。当院では患者様のお口の中の状況に合わせた治療方法をご提案いたしますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。
ホワイトニング前に気をつけたい むし歯の治療
2024/04/10
今回は、むし歯の治療についてご紹介します。ホワイトニングの処置を受ける前には必ずむし歯がないか確認を受けることをおすすめしています。万が一むし歯があった場合、そのむし歯の進行状況によって治療内容が変わり、それがホワイトニングの処置に影響することもあるからです。むし歯は進行状況事に症状も異なり、治療の方法も変わってきます。
段階ごとに異なるむし歯の治療
むし歯の進行は5つの段階に分かれますが、それぞれで治療の方法も異なります。
・Co(初期むし歯)
初期段階のむし歯なので、フッ素などによる再石灰化によってエナメル質を修復できる可能性があります。ご自宅でのセルフケアで高濃度のフッ素が配合された歯磨き粉を使っていただく、歯科医院でフッ素塗布を行う、歯科医院で定期的にむし歯が進行していないかのチェックやクリーニングを行うことで、これ以上むし歯が進行しないように踏みとどまれる可能性が高くなります。
・C1
エナメル質のごく狭い範囲に穴があいた状態ですが、Coと同様に経過観察でよい場合と歯科医院での治療が必要な場合があります。歯科医院で治療をするときは、むし歯になっている範囲の歯質を専用の器械で削り、そこにプラスチック(コンポジットレジン)の詰め物をします。
・C2
エナメル質の内側にある象牙質にまでむし歯が進んでいるので、必ず歯科医院での治療が必要です。C1の治療と同様にむし歯になっている箇所を削り、歯質を補う処置をします。削った範囲が広い場合はインレー(詰め物)もしくはクラウン(被せ物)の作製が必要になります。これらの修復物を作製するときには歯を削った後に型どりを行い、それをもとにした模型上でつくります。
・C3
象牙質の更に内側にある歯髄(歯の神経が入っている場所)にまでむし歯が進んでいるため、神経の処置も必要になります。神経を除去したあとに管の中を綺麗に掻把し、さらに管の空間を埋めるためのゴム状の材料を詰めていきます。その後クラウンを被せるための土台を作製してから型どりをし、完成したクラウンを被せます。神経の処置には通常複数回のご来院が必要です。
・C4
歯冠(歯ぐきの上の見える部分)のほとんどが崩壊して歯の根だけが残された状態なので、基本的に歯を残すことは難しいとされています。この場合は抜歯の適応となります。
まとめ
今回は、むし歯の治療についてご紹介しました。ホワイトニングの処置を受ける前には必ずむし歯がないかを歯科医院でチェックしてもらうとともに、むし歯を予防してお口の健康を守ることも意識していきましょう。
当院は、多数の症例実績を誇るホワイトエッセンス加盟医院です。ホワイトニングのご予約、お問合せはお電話で承っております。