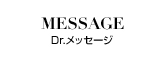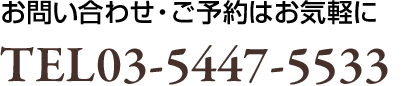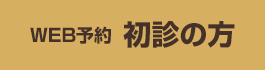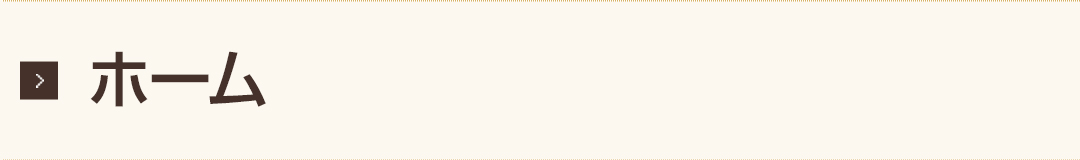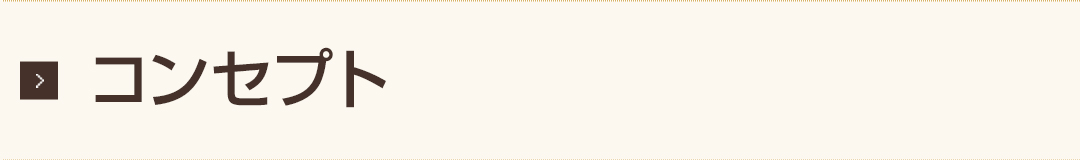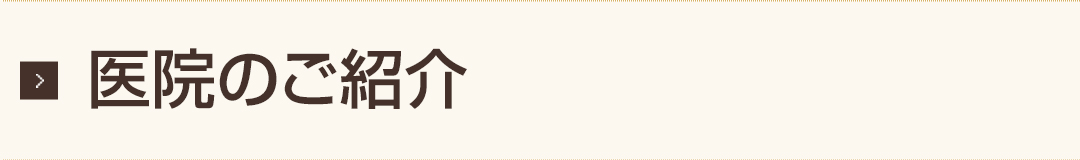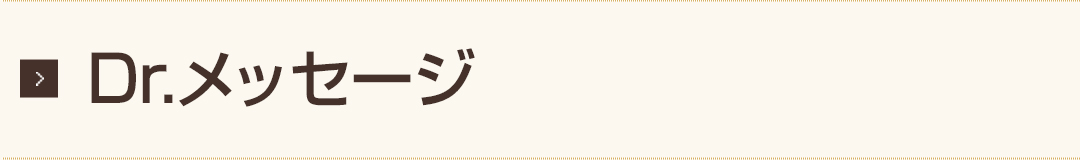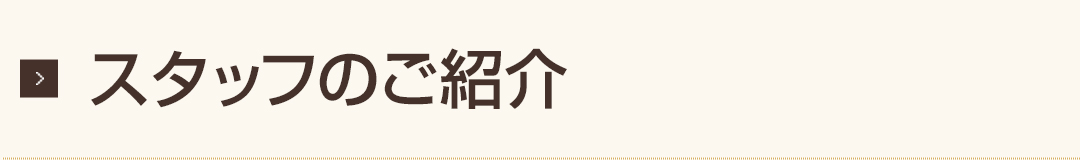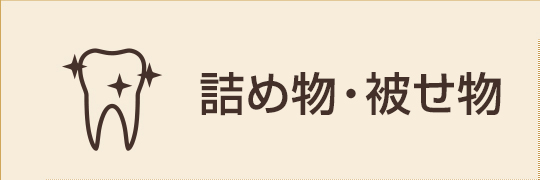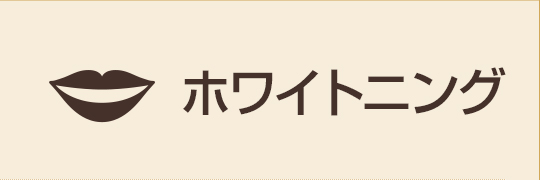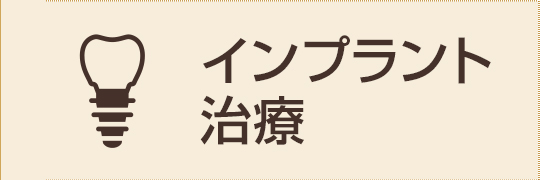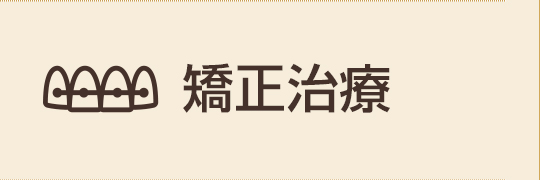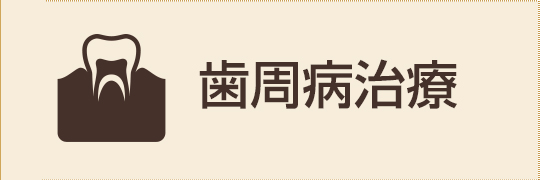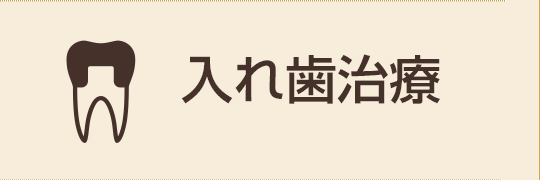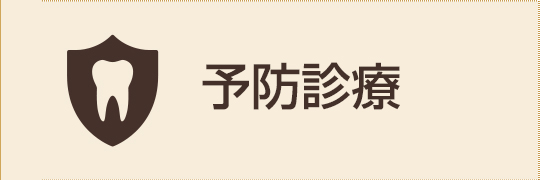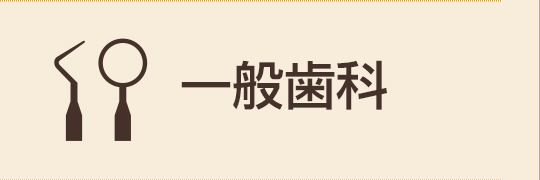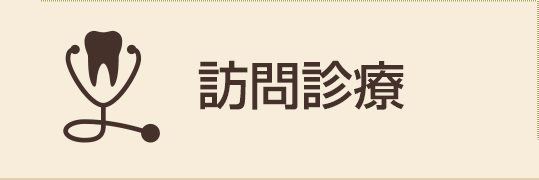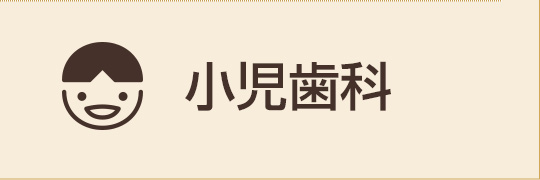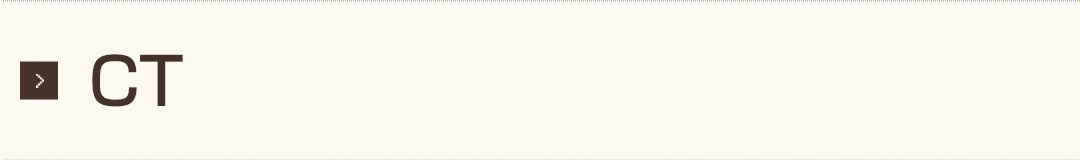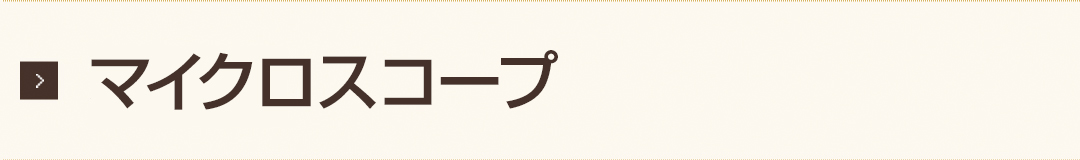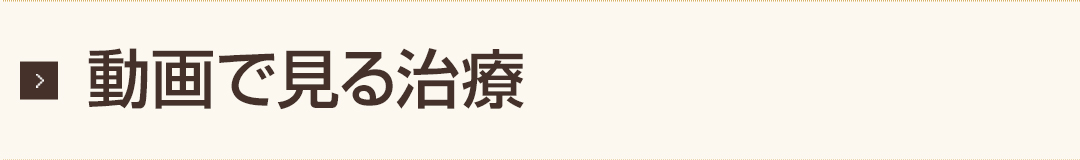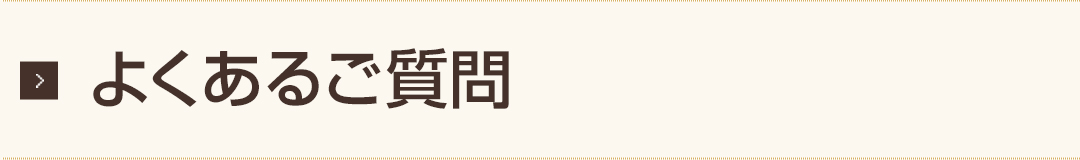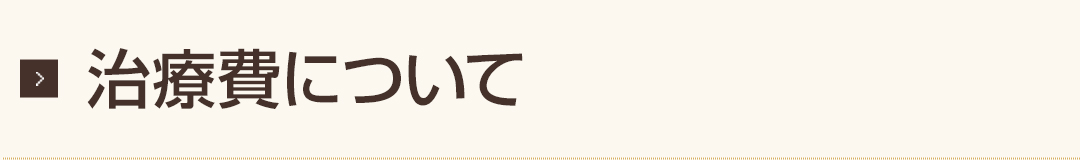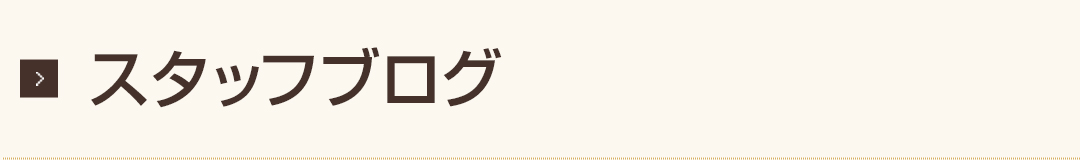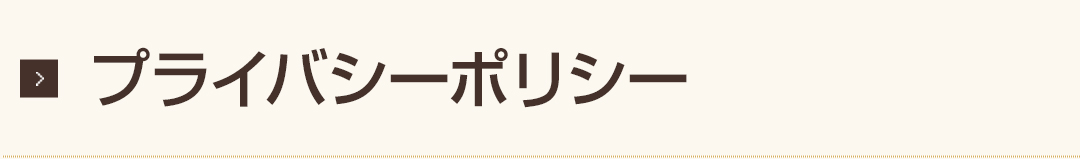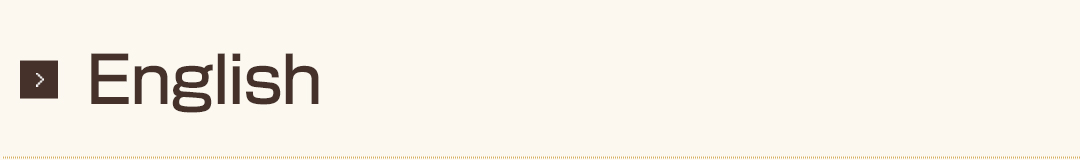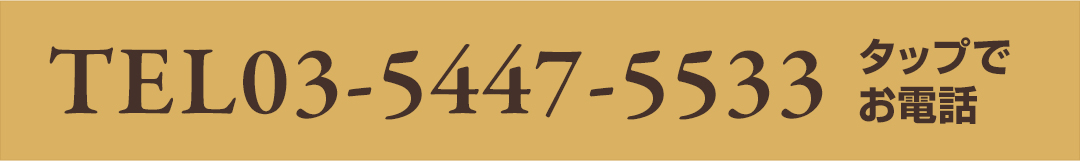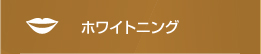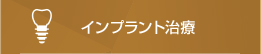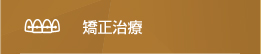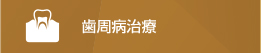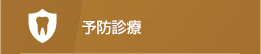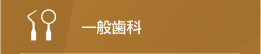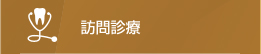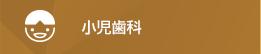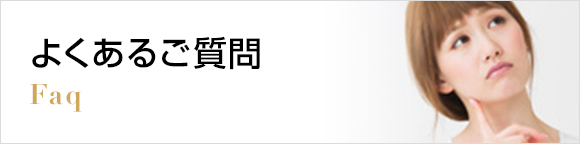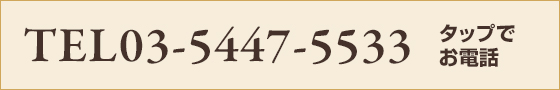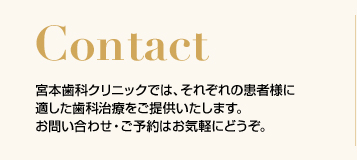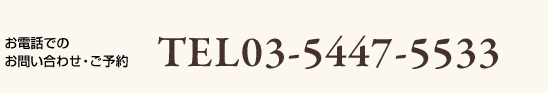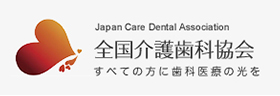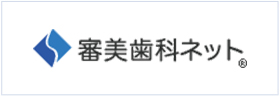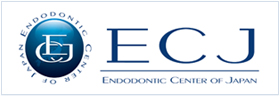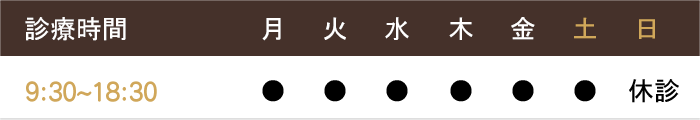フッ素を上手に活用してむし歯予防を!
2025/05/16
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、むし歯予防に欠かせない「フッ素」の活用方法についてご紹介します。
フッ素の活用で大切なこと
むし歯予防に効果的な成分として知られるフッ素は、歯を強くし、むし歯のリスクを減らすために幅広く活用されています。効果的に取り入れるには、使い方がとても重要です。自宅でできるケアと、歯科医院での専門的なケアの両方を取り入れるようにしましょう。
自宅でできるフッ素ケア
自宅でフッ素を活用する代表的な方法は、「フッ素配合歯みがき剤」の使用です。市販されている歯みがき粉の多くにはフッ素が含まれており、毎日の歯みがきで継続的にフッ素を取り込むことができます。ポイントは、「歯みがき後にゆすぎすぎない」ことです。口をしっかりゆすぎすぎると、せっかく歯に残ったフッ素も一緒に流れてしまうため、水は少なめで軽く1回すすぐ程度がおすすめです。
また、年齢に応じたフッ素濃度の歯みがき粉を使うことも大切です。小さなお子さんには低濃度、大人には高濃度のものを選びましょう。近年では「高濃度フッ素配合(1450ppm)」の歯みがき剤も市販されており、むし歯リスクが高い方には特におすすめです。
さらに、フッ素入りのうがい薬(洗口液)も自宅ケアに有効です。歯みがきとは別に夜寝る前などに使用することで、より長時間フッ素を口の中に留めることができます。
歯科医院でのフッ素塗布
自宅でのケアに加えて、歯科医院で行うフッ素塗布も非常に効果的です。専門的なフッ素塗布は、自宅の歯みがき粉よりも高濃度のフッ素を直接歯の表面に塗布することで、歯の表面を強化し、むし歯への抵抗力を高めることができます。
まとめ
フッ素は、継続して使うことが最も大切です。日頃のセルフケアに加えてプロフェッショナルなケアを組み合わせることで、歯を守る力を最大限に引き出すことができます。
自宅で毎日のケアを続けながら、定期的に歯科医院で専門的なフッ素塗布を受け、むし歯の予防効果を高めましょう。
フッ素の3つの働きとは?むし歯予防に欠かせない理由
2025/05/07
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、むし歯予防に欠かせない「フッ素」の働きについてご紹介します。
フッ素とは
みなさんは、歯科医院や歯みがき粉などでよく目にする「フッ素」について、どんな働きがあるかご存知でしょうか?フッ素は、むし歯予防にとても効果的な成分であり、歯科医療の現場では長年にわたって活用されています。特に子どもから大人まで、幅広い年齢層で取り入れたい予防手段のひとつです。
① 歯を強くする「再石灰化の促進」
私たちの歯は、食事や飲み物を摂るたびに、酸によって表面のエナメル質が少しずつ溶けています。これを「脱灰」といいます。しかし、唾液の働きによって、失われた成分が再び歯に取り込まれ、修復される「再石灰化」というプロセスも自然に起こっています。ここで重要なのがフッ素の存在です。
フッ素は、この再石灰化を助ける作用があります。フッ素が歯に取り込まれることで、エナメル質がより硬く、酸に強い状態に修復されやすくなるのです。これによりむし歯の進行を防ぐだけでなく、初期のむし歯であれば自然に回復する可能性も高まります。
② むし歯菌の活動を抑える「抗菌作用」
むし歯の原因となるのは、「ミュータンス菌」などの細菌が糖を分解して酸をつくり、その酸が歯を溶かすことにあります。フッ素には、むし歯菌の活動を抑える抗菌作用があります。具体的には、フッ素がむし歯菌の代謝を抑制することで、酸の産生量を減少させます。酸が減れば歯が溶けるリスクも下がるため、むし歯の予防につながるのです。このようにフッ素は、歯を守るだけでなく、むし歯の原因そのものにも働きかける優れた成分です。
③ 歯質を強化して「むし歯に強い歯をつくる」
歯の表面は主に「ハイドロキシアパタイト」という成分からできています。これ自体は酸に弱く、むし歯になりやすい構造です。しかし、フッ素が歯に取り込まれると、「フルオロアパタイト」という構造に変わります。これは、酸に強く溶けにくい性質をもつため、むし歯に対する耐性が高くなります。
つまり、フッ素は歯を「むし歯になりにくい状態」に変えてくれるのです。特に、生えたばかりの永久歯や乳歯は柔らかくむし歯になりやすい時期なので、フッ素による予防はとても有効です。
まとめ
今回ご紹介したように、フッ素にはむし歯予防に欠かせない3つの働きがあります。そして、毎日のケアにフッ素を取り入れることでむし歯を防ぎ、歯を健康に保つことができます。フッ素の活用方法は次回以降のブログでご紹介します。
むし歯になりやすい人となりにくい人は何が違う?
2025/04/18
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、むし歯になりやすい人となりにくい人の違いについてご紹介します。
むし歯になりやすい人の特徴
むし歯は誰にでも起こり得るものですが、実は「むし歯になりやすい人」と「むし歯になりにくい人」がいます。では、その違いはどこにあるのでしょうか?
・歯磨きが不十分
むし歯は、口の中に残った食べかすやプラーク(歯垢)に含まれる細菌が酸を作り、歯を溶かすことで発生します。磨き残しが多いと、むし歯のリスクが高まります。
・甘いものや間食が多い
砂糖を含む食品や飲料を頻繁に摂取すると、口内の細菌が酸を作りやすくなります。また、間食の回数が多いと口の中が常に酸性になり、むし歯のリスクが上がります。
・唾液の量が少ない
唾液は口内の汚れを洗い流し、歯を再石灰化する役割を持っています。口が乾燥しやすい人や、唾液の分泌量が少ない人は、むし歯になりやすい傾向があります。
・歯並びが悪い
歯並びが悪いと歯と歯の間に食べかすやプラークがたまりやすくなり、歯ブラシが届きにくいため、むし歯のリスクが高まります。
・歯の質が弱い
エナメル質が薄い人や歯の再石灰化がうまくいかない人は、むし歯になりやすい傾向があります。
むし歯になりにくい人の特徴
・丁寧な歯磨きを習慣化している
歯ブラシだけでなくデンタルフロスや歯間ブラシを使って、歯と歯の間の汚れもしっかり落とすことが大切です。
・食生活が整っている
砂糖を控えめにしバランスの良い食事を心掛けることで、むし歯のリスクを減らせます。また、よく噛むことで唾液の分泌を促すことも重要です。
・唾液の分泌が多い
唾液が多い人は口の中を清潔に保ちやすく、むし歯のリスクが低くなります。ガムを噛んだり、水分を十分に摂ったりすると、唾液の分泌が促進されます。
・定期的に歯科検診を受けている
むし歯になりにくい人は、歯科医院での定期検診やクリーニングを受けています。早期発見・早期治療が、むし歯を防ぐポイントです。
まとめ
むし歯になりやすい人となりにくい人の違いは、生活習慣や口腔ケアの方法に大きく左右されます。毎日のケアを見直し、定期的な歯科検診を受けることで、健康な歯を維持しましょう。
妊娠中の親知らずのトラブル、抜歯はできる?
2025/04/04
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、妊娠中の親知らずのトラブルへの対処法と、抜歯の可否についてご紹介します。
妊娠中に親知らずのトラブルが起こりやすい理由
妊娠中は、ホルモンバランスの変化により歯ぐきが腫れやすくなります。特に親知らずの周囲は磨きにくく細菌が繁殖しやすい環境のため、歯ぐきが腫れるなどの炎症が起こりやすいのです。
主なトラブルの症状
・親知らずの周囲の腫れや痛み
・口が開きにくい
・歯ぐきが赤く腫れ、膿がたまる
・発熱や全身の倦怠感
このような症状がある場合、すぐに歯科医院で相談しましょう。
妊娠中に親知らずを抜歯できる?
妊娠中の抜歯は可能ですが、慎重に判断する必要があります。妊娠初期(~15週)と後期(28週~)は、母体への負担が大きいため、抜歯は避けた方がよいとされています。比較的体調が安定している妊娠中期(16~27週)であれば、歯ぐきの切開を伴わない簡単な抜歯は可能です。ただし、基本的には応急処置にとどめ、本格的な抜歯は出産後に行うのが一般的です。
妊娠中の親知らずトラブルへの対処法
抜歯をしない場合でも、症状を和らげる方法があります。
1.口腔内を清潔に保つ
・親知らずの周囲を丁寧に磨く
・デンタルリンスを活用する
2.炎症を抑える
・歯科医院で抗菌薬や痛み止めを処方してもらう(妊娠中でも使用できる薬を選択)
・腫れている部分を冷やす
3.食事の工夫
・刺激の少ない柔らかい食事を選ぶ
・糖分の多い食べ物を控える
まとめ
妊娠中に親知らずのトラブルが起きた場合、まずは歯科医院に相談しましょう。妊娠中期であれば簡単な抜歯は可能ですが、基本的には応急処置を行い、本格的な抜歯は出産後にするのが一般的です。お口のトラブルを防ぐために、日頃からのケアを大切にしましょう。
妊娠中に局所麻酔をしても大丈夫?
2025/03/21
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、妊娠中に局所麻酔をしてもよいのか、その安全性についてご紹介します。
局所麻酔とは?
局所麻酔は、体の一部分だけの感覚を一時的に麻痺させることで痛みを感じずに処置を受けられるようにする方法です。歯科で使われる主な局所麻酔には以下の3種類があり、処置の内容によって使い分けられます。
・表面麻酔
歯ぐきの表面に麻酔薬を塗布し、感覚を鈍くする方法です。注射の痛みを軽減する目的で使われることが多く、負担が少ない麻酔方法です。
・浸潤麻酔
歯ぐきに直接麻酔液を注射し、歯やその周辺の組織を麻痺させる方法です。むし歯の治療や歯の根の治療など、比較的浅い部分の処置でよく使われます。
・伝達麻酔
神経が集まる場所に麻酔を注射し、広範囲を麻痺させる方法です。主に親知らずの抜歯や顎の奥深くの処置で使用されます。
局所麻酔が必要になる歯科処置
局所麻酔を使用する歯科治療には、下記のようなものがあります。
・むし歯の治療
中程度から重度のむし歯の治療では、歯を削る際の痛みを和らげるために浸潤麻酔が使われます。
・歯の根の治療(根管治療)
歯の神経が炎症を起こしている場合、痛みを伴う治療になるため麻酔が欠かせません。
・親知らずの抜歯
表面麻酔と浸潤麻酔のみで対応できるケースも多くありますが、親知らずが深く埋まっている場合などには、伝達麻酔を使って広範囲を麻痺させて処置を進めることもあります。
妊娠中に局所麻酔をしても大丈夫?
妊娠中に歯科治療を受ける際に「局所麻酔を使っても赤ちゃんに影響はないのだろうか?」と心配される方が多いかもしれません。しかし、実際には歯科で使用される局所麻酔は、妊婦さんや胎児に対して安全とされています。歯科で使用される局所麻酔は、薬液の量が非常に少なく、麻酔が効く範囲も限られています。そのため、全身に影響が及ぶことはほとんどありません。
一方で、麻酔の影響を心配して痛みを我慢し続けることは、妊婦さん自身にとって大きなストレスとなります。ストレスは血圧の上昇やホルモンバランスの乱れを引き起こし、母体や胎児に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、必要な場合には麻酔を使用して適切な治療を受けることが重要です。
まとめ
妊娠中の歯科治療では、局所麻酔の安全性について心配になるかもしれませんが、歯科で使用される麻酔は少量で、胎児に影響を与えることはほとんどありません。適切な治療を受けることで妊娠中の口腔内トラブルを早期に解決し、母体と胎児の健康を守りましょう。