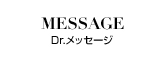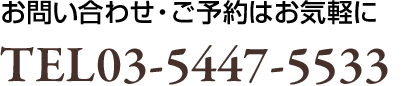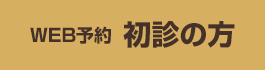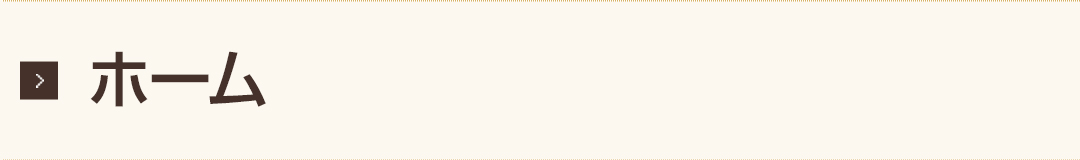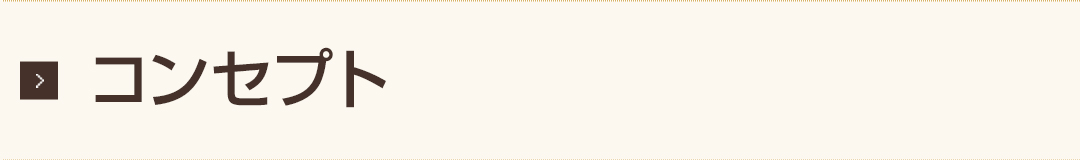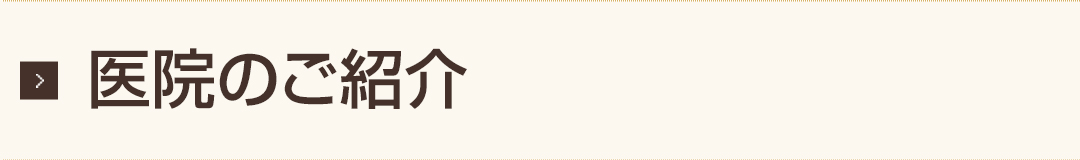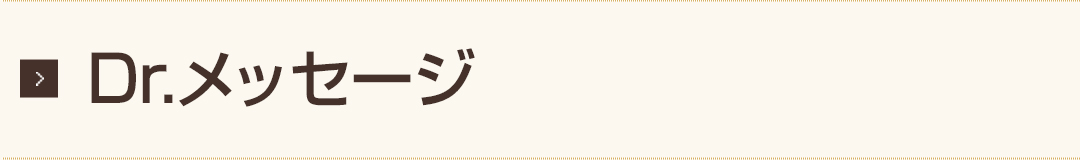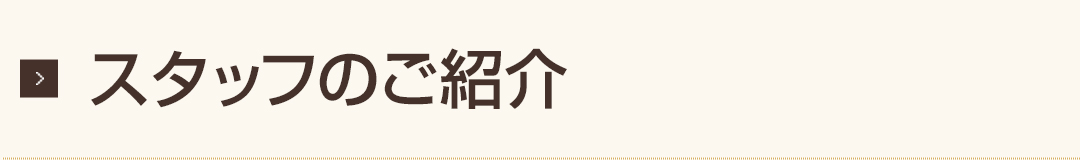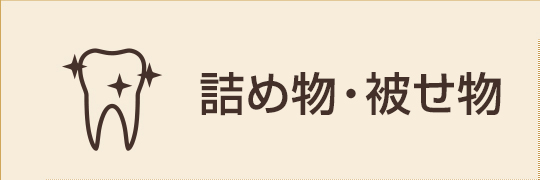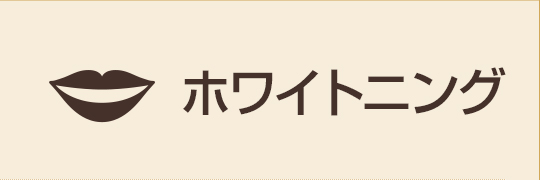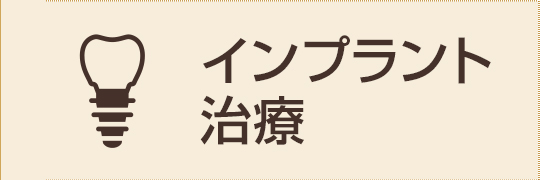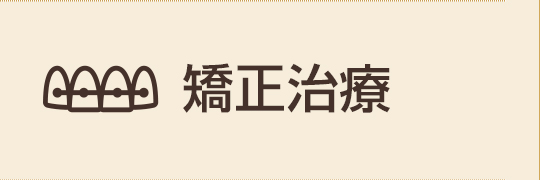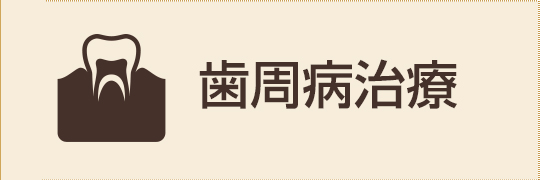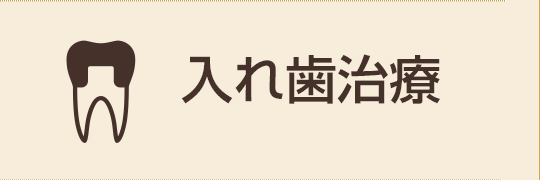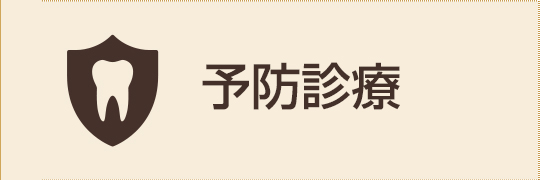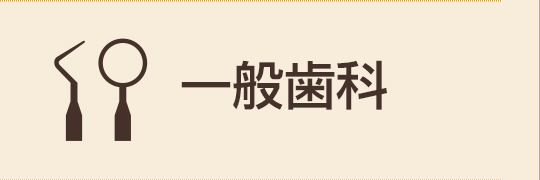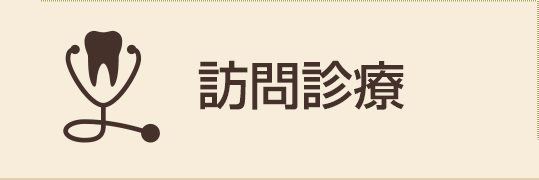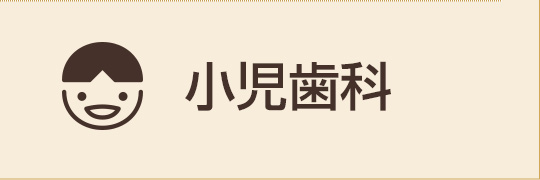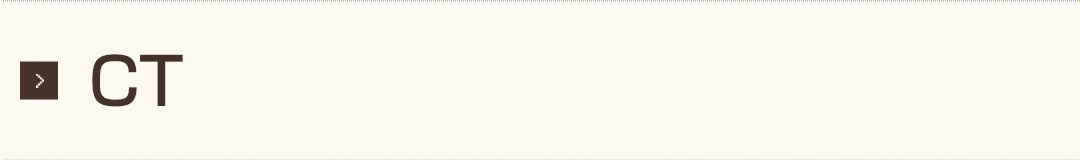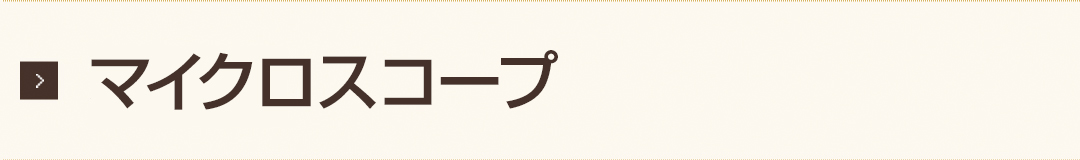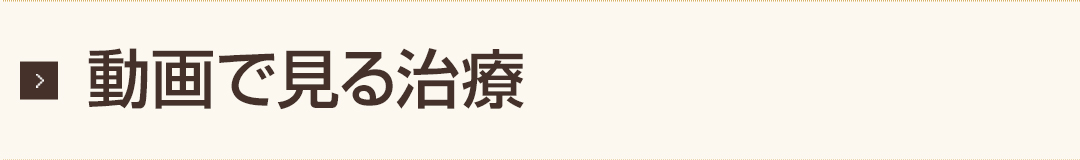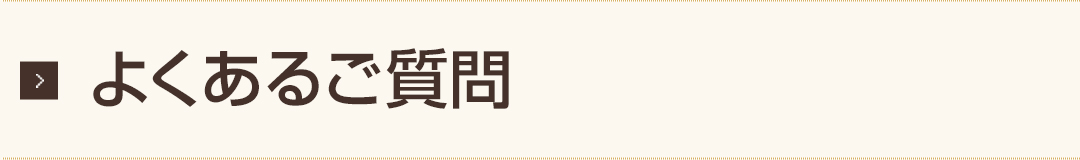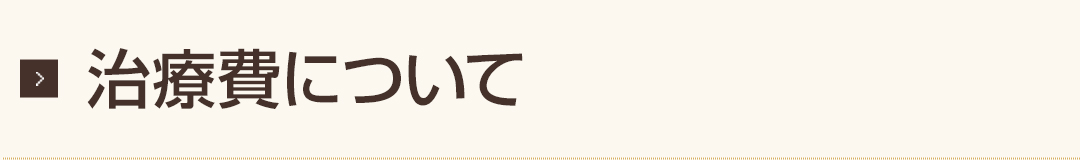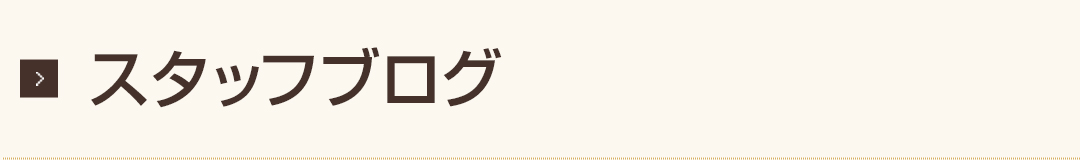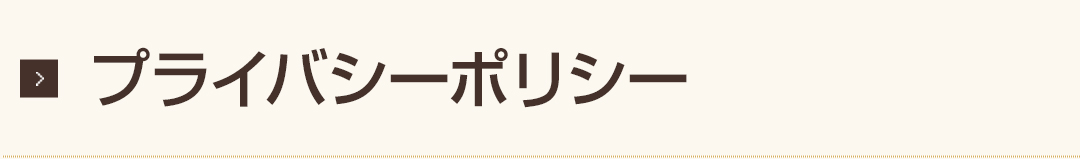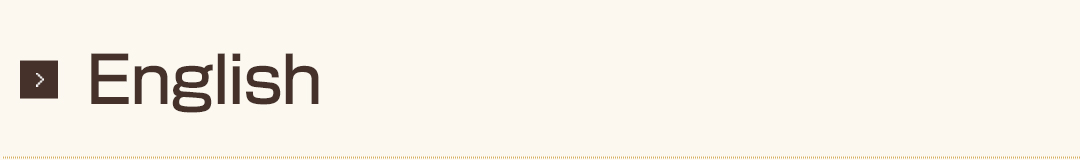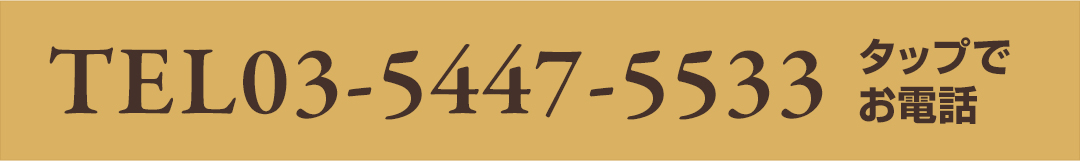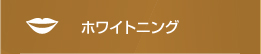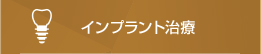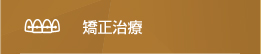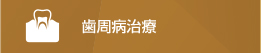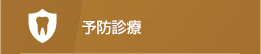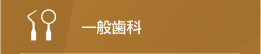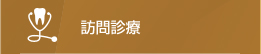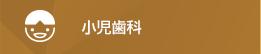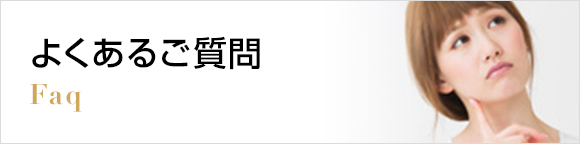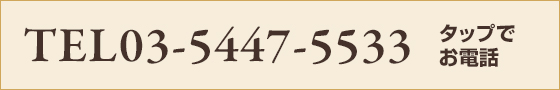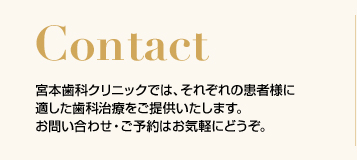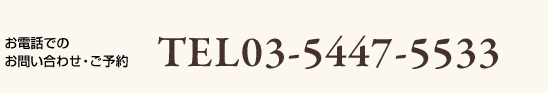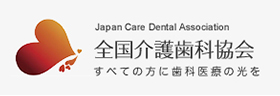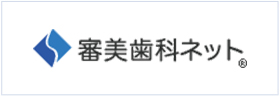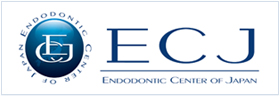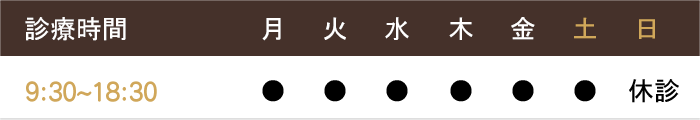非加熱式煙草や電子煙草は歯周病に影響を与えるのか?
2025/01/06
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、非加熱式煙草や電子煙草と歯周病との関係についてご紹介します。
歯周病と煙草の関係
歯周病は、歯を支える歯ぐきや骨が炎症によって徐々に破壊される病気です。進行すると歯を失う原因となるだけでなく、糖尿病や心疾患、早産など全身への影響も報告されています。煙草はこの歯周病の進行を加速させる大きな要因とされており、煙草が歯周病のリスクを高めることも広く知られています。しかし、非加熱式煙草や電子煙草の登場により、「従来の煙草よりも健康への影響が少ない」というイメージが持たれることもあります。では、これらの新しいタイプの煙草は歯周病に影響を与えるのでしょうか?
非加熱式煙草や電子煙草は安全なのか?
非加熱式煙草や電子煙草は、従来の紙巻き煙草に比べて「煙を発生させない」「有害物質の量が少ない」とされています。しかし、完全に無害というわけではありません。実際、これらの煙草にも歯周病に悪影響を与える要素が含まれています。
・ニコチンの影響
非加熱式煙草や電子煙草にも多くの場合、ニコチンが含まれています。ニコチンは血管を収縮させる作用があり、歯ぐきへの血流を低下させるため、歯周病が進行しても歯ぐきの出血や炎症といった症状が現れにくく、病気が見過ごされやすくなる可能性があります。
・炎症反応への影響
煙草に含まれる物質は免疫機能を低下させ、歯周病菌に対する防御力を弱めます。非加熱式煙草や電子煙草も完全にこれらの影響を排除するわけではないため、歯周組織の炎症を悪化させるリスクがあります。
・口腔内の乾燥
電子煙草の蒸気は、口腔内を乾燥させる可能性があります。唾液は口腔内の細菌を洗い流す役割を持つため、乾燥することで歯周病菌が繁殖しやすい環境が作られる可能性があります。
まとめ
非加熱式煙草や電子煙草は従来の煙草に比べると健康への影響が軽減されているとされますが、歯周病に対する影響が完全になくなるわけではありません。特にニコチンの存在や口腔内環境への影響を考えると、これらの新しい煙草も慎重に扱う必要があります。健康な歯と歯ぐきを保つためには禁煙を含む生活習慣の見直しと、定期的な歯科検診を心がけましょう。
喫煙と歯周病の密接な関係
2024/12/25
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、喫煙と歯周病の関係についてご紹介します。
喫煙が歯周病に及ぼす影響
喫煙は健康全般に悪影響を及ぼすことで知られていますが、口腔内にも大きな影響を与えます。特に歯周病との関連は深く、喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病になるリスクが高いとされています。また、歯周病の治療効果を低下させる原因にもなります。歯周病は、歯を支える歯ぐきや骨が炎症によって破壊される病気です。初期段階の歯肉炎を放置すると進行して歯周炎となり、最悪の場合は歯を失うことにつながります。
・歯茎の血流を悪化させる
煙草に含まれるニコチンや一酸化炭素は血管を収縮させ、歯ぐきへの血流を減少させます。その結果、歯ぐきの免疫力が低下し、細菌感染が起こりやすくなります。さらに、歯周病の初期症状である歯ぐきの腫れや出血が目立たなくなるため、発見が遅れることがあります。
・歯周病菌の繁殖を助ける
喫煙は口腔内の環境を変化させ、歯周病菌が繁殖しやすい状態を作ります。また、唾液の分泌量が減少して口腔内の自浄作用が弱まるため、プラークや歯石がたまりやすくなります。
・治療効果を妨げる
喫煙者は非喫煙者に比べ、歯周病の治療効果が得られにくい傾向があります。歯ぐきの回復には血流が重要ですが、喫煙はこれを阻害します。さらに、インプラント治療や歯周外科手術後の治癒にも悪影響を与えることが報告されています。
歯周病リスクを減らすために
・禁煙を始める
禁煙によって血流が改善し、免疫力が回復することで、歯ぐきの健康が向上します。また、歯周病治療の効果も高まりやすくなります。
・定期検診を受ける
喫煙者は歯周病の進行が早いため、歯科医院での定期検診やプロフェッショナルケアが不可欠です。必要に応じて適切な治療を受けましょう。
・セルフケアを徹底する
歯磨きやフロス、歯間ブラシを使い、口腔内を清潔に保つことも大切です。プラークがたまりにくい環境を作ることで、歯周病の進行を防ぐことができます。
まとめ
喫煙は歯周病を悪化させる大きな要因であり、健康な歯を保つためには喫煙習慣の見直しが必要です。禁煙することで口腔内の健康を取り戻すだけでなく、全身の健康改善にもつながります。歯周病を予防し治療効果を高めるために、ぜひ禁煙を検討してみましょう。
歯と口の健康のために 「噛む回数」がもたらす効果とは
2024/12/20
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、食事中の噛む回数と歯や口の健康との関係についてご紹介します。
なぜ噛むことが大切なのか?
食事のとき、食べ物を何回噛んでいますか?忙しい日々の中で、噛む回数を意識して食事をする人は少ないかもしれません。しかし、「噛む」行為は単なる食事の一部ではなく、口腔内から始まる消化・吸収のプロセスにおいて重要な役割を果たしています。
・歯や顎の健康を保つ
噛むことで歯や顎に適度な刺激が加わり、顎の骨や歯周組織が強化されます。また、唾液の分泌が促進され、むし歯や歯周病を予防する効果も期待できます。
・消化を助ける
食べ物を細かく噛み砕くことで、消化酵素が働きやすくなり、栄養を効率よく吸収できます。これらの作用により、胃腸への負担が軽減されます。
・脳の活性化
噛む動作は脳への刺激となり、記憶力や集中力の向上に繋がります。特に成長期の子どもには重要な習慣です。
1口につき何回噛むのが理想?
一般的に、1口につき30回程度噛むことが理想とされています。噛む回数を増やすことで食べ物が細かくなり、唾液と十分に混ざることで消化がスムーズに進みます。ただし、食べ物にはさまざまな硬さのものが存在するため、軟らかいものでも30回噛むのは難しいと感じる方も多いでしょう。もちろん、食品の硬さによって噛む回数も変わってきます。食事の時間が20~30分程度かかるようにすると満腹感を得られるともいわれているため、時間を一つに目安にするのもよいでしょう。また、軟らかいものばかりを食べるのではなく、ある程度硬さがあって30回程度噛めるものを意識的に取り入れていきましょう。
まとめ
歯と口の健康を守るためには、「何回噛むか」を意識することが大切です。噛む回数を増やすことで全身の健康にも繋がります。1口30回を目標に、食事をゆっくり楽しみながら歯や顎の健康をサポートしましょう。
唾液腺マッサージで口腔環境を健康に
2024/12/16
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、唾液腺マッサージの方法やメリットについてご紹介します。
唾液腺マッサージとは?
唾液は私たちの口腔内を健康に保つために欠かせない役割を果たしています。唾液がしっかりと分泌されることで口の中が潤い、食べ物の消化を助けたり、むし歯や口臭を予防する効果がありますが、ストレスや加齢、生活習慣などの影響で唾液の分泌量が減少してしまうこともあります。そのようなときに役立つのが「唾液腺マッサージ」です。唾液腺マッサージは、口腔内に唾液を分泌する唾液腺を刺激することで、唾液の分泌を促進する方法です。
唾液腺の種類
唾液腺は大きく分けて3種類あります。これらの唾液腺をやさしく刺激することで、唾液の分泌を助けることができます。
・耳下腺(じかせん)
耳の少し前、頬骨の下に位置しており、さらさらとした唾液を分泌します。
・顎下腺(がっかせん)
顎の下にあり、やや粘り気のある唾液を分泌します。
・舌下腺(ぜっかせん)
舌の下にあり、少量の粘り気のある唾液を分泌します。
唾液腺マッサージの方法
唾液腺マッサージは簡単で、1回数分程度で行えます。3か所のマッサージを組み合わせて行うことで、唾液の分泌を効果的に促進できるでしょう。
・耳下腺
両手の指先を耳の前、頬骨の下あたりに置きます。ゆっくりと円を描くように10回ほどやさしく押しながら回します。
・顎下腺
顎の骨の内側に両手の指を当てます。内側から外側に向かって10回ほど押し流すようにマッサージします。
・舌下腺
親指を顎の下に、他の指を顎の上に置きます。親指で押し上げるように10回ほど軽く刺激します。
唾液腺マッサージのメリット
唾液腺マッサージには以下のようなメリットがあります。
・ドライマウスの改善
唾液の分泌が少ないと感じる方におすすめです。
・口臭の予防
唾液が細菌を洗い流し、口臭の発生を抑える効果があります。
・むし歯や歯周病の予防
唾液の抗菌作用でむし歯や歯周病のリスクを軽減できます。
まとめ
唾液腺マッサージは、唾液の分泌を促進し、口腔内の健康を維持するための簡単なセルフケア方法です。ドライマウスや口臭が気になる方は、ぜひ日常生活に取り入れてみてください。気になる症状が続く場合は、歯科医院で相談しましょう。
唾液の働きを守るためにできること
2024/12/11
「ミニマルインターベンション(MI)」の考え方には5つの項目が掲げられており、その中の一つに「患者様への教育」があります。その代表例でもある口腔衛生指導(OHI)は歯科医院において欠かせない役割を果たしており、単に歯を磨く方法を教えるだけでなく、患者様の全身の健康に直結する重要なプロセスです。今回は、唾液の働きを守るためにできることについてご紹介します。
さまざまな唾液の働き
唾液は口腔内の健康を保つだけでなく、消化を助けたり、感染症を予防したりと、私たちの体に多くの恩恵をもたらしています。しかし、生活習慣やストレス、加齢によって唾液の分泌量が減少すると口腔内環境が悪化し、むし歯や歯周病、口臭といったトラブルが起こりやすくなります。では、唾液の働きを守るためにはどのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。
よく噛む習慣をつける
食事の際によく噛むことは、唾液分泌を促進する最も簡単で効果的な方法です。噛む回数が増えると唾液腺が刺激され、唾液が多く分泌されます。特に硬めの食品や野菜を取り入れると、自然と咀嚼回数が増えます。また、噛むことは消化の助けにもなり、胃腸の負担を軽減するメリットもあります。
水分補給を忘れない
唾液の主成分は水分です。そのため、体内の水分が不足すると唾液の分泌量が減少してしまいます。特にエアコンの効いた部屋や乾燥した環境では知らず知らずのうちに体が脱水状態に近づいていることがあるため、こまめに水分を摂取することが大切です。1日あたり約1.5~2リットルの水を目安に摂取するとよいでしょう。なお、糖分が多い飲料やアルコールは逆効果になることがあるため、純粋な水やお茶を選ぶのがおすすめです。
口腔ケアを徹底する
適切な口腔ケアは、唾液の働きをサポートします。歯磨きや舌磨きを習慣にすることで口腔内を清潔に保ち、唾液の抗菌作用や浄化作用を十分に発揮させることができます。特に舌苔は口臭の原因になるため、専用の舌ブラシを使って優しく取り除きましょう。また、ガムを噛むこともおすすめです。ガムを選ぶ際は、無糖のものやキシリトールが配合されているものを選んでみましょう。
まとめ
唾液が十分に分泌されている状態は、健康な口腔環境の維持に欠かせません。よく噛む習慣や水分補給、口腔ケアを意識的に行うことで、唾液の働きを守ることができます。日々の生活に少しの工夫を加え、口腔内のトラブルを防ぎましょう。